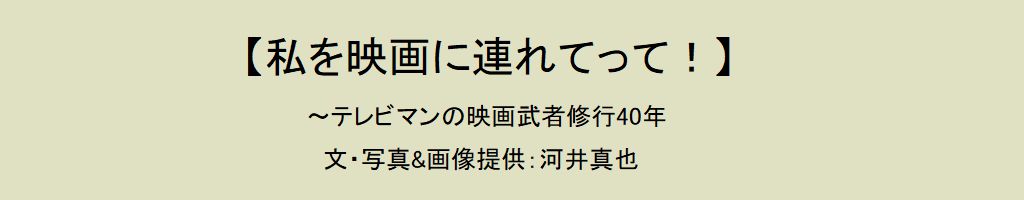
1981年にフジテレビジョンに入社後、編成局映画部に配属され「ゴールデン洋画劇場」を担当することになった河井真也さん。そこから河井さんの映画人生が始まった。『南極物語』での製作デスクを皮切りに、『私をスキーに連れてって』『Love Letter』『スワロウテイル』『リング』『らせん』『愛のむきだし』など多くの作品にプロデューサーとして携わり、劇場「シネスイッチ」を立ち上げ、『ニュー・シネマ・パラダイス』という大ヒット作品も誕生させた。テレビ局社員として映画と格闘し、数々の〝夢〟と〝奇跡〟の瞬間も体験した河井さん。この、連載は映画と人生を共にしたテレビ局社員の汗と涙、愛と夢が詰まった感動の一大青春巨編である。
これまで演劇人と何本か映画を創ってきた。
俳優の仕事のメイン土俵は、演劇か映画かテレビドラマか……大別すると3つだろうか。
ぼくはテレビ局にいて主に映画製作をやってきたので、テレビディレクターと映画の関係は間近で見てきた。ただ、元フジテレビのディレクターだった五社英雄さんのように、映画界に身をおいてからは『鬼龍院花子の生涯』(1982)など堂々とした「映画監督」になった方もいる。
テレビドラマの映画化においては、キャスト、スタッフも共通のことが多くなり、ドラマでは出来なかった大きな仕掛けを制作費を費やして作ることが多くなった。キャラクター設定、ストーリーも大きく変えてしまうとドラマの映画化ではなく「オリジナル」ものに近くなってしまう。
一方、演劇の映画化はあまり多くはない。それでも、つかこうへい戯曲の映画化『蒲田行進曲』(深作欣二監督/1982)のように傑作も幾つか誕生した。
その当時、野田秀樹主宰の<夢の遊眠社>が大人気で、その中でも『走れメルス』を映画化しようとしたことがあった。舞台は、野田さんがまだ東大在学中に初演(1976)されたものだが、ぼくが観たのは第30回公演『走れメルス~少女の唇からはダイナマイト!』(1986/本多劇場)だろうか。スピード感、劇的な展開、言葉遊びとの見事なハーモニーの中で、この凝縮された異次元体験を映画で出来れば……と思ったものだ。岡田裕介プロデューサー(1988年からは東映)が熱心に野田秀樹監督映画を! と動かれていて『走れメルス』は印刷台本まで作った。映画『蒲田行進曲』は「蒲田」という松竹の撮影所聖地の名前がついているが、内容は東映の「大部屋」の俳優たちの話。監督も東映の『仁義なき戦い』などの名匠・深作欣二とあって東映色が強いが配給は松竹で、角川&松竹映画だった。
『走れメルス』の野田さんが書いたシナリオはとても面白かったが、長かった。5時間くらいのボリュームだっただろうか。演劇は映像と違い「端折る」シーンも多い。その「間」を観客に考えさせることもある。映画のように場面設定が100回(シーン)以上変わることもなかなか出来ない。シナリオは想像以上の場面展開が映像として表現されていたように思う。
野田秀樹さんと、岡田裕介さんと一緒に最後に会った時、野田さんから「短くするならあまり映画にするのは……」(表現の規制などもあったかと)というようなことで、そこでリセットした記憶がある。『走れメルス』はその後、野田さんの「野田地図/NODA・MAP」でも再演されていてやはり傑作である。今、思い起こすと、正直なところ、あのダイナミックな舞台をどのように「映画」で表現出来るかの具体はぼくには見えていなかったように思う。


















































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















