「映画評論」という言葉も、日本ではあまり聞かなくなってしまったが。本来は重要なところである。欧米なら、この批評家の見識が今も、大事である。特に演劇においてなどは、この評価が直接の動員にも大きく影響するだろう。今も、BBCや世界の評論家が選ぶ映画のベストは、「世界の歴代映画ベスト100」や「今世紀のベスト100」など大きな影響力を持つ。まだ100数十年の歴史しかない「映画」ではあるが、美術や小説、音楽のように後世に語り継がれていく作品もあるだろう。そういう作品をいち早く発見し、映画祭で上映。そしてその後は優秀作品に賞を与え、後世まで称えていく……。
『Love Letter』は日本の公開から4年遅れて韓国で上映になった。このきっかけはモントリオール世界映画祭で観客賞をもらっていたからである。
1998年にようやく韓国で日本映画公開(開放)が始まり、最初は3大(4大とも)国際映画祭(カンヌ・ベルリン・ヴェネチア)グランプリ作品からスタートした。
『HANA-BI』(北野武監督)、『影武者』(黒澤明監督)、『うなぎ』(今村昌平監督)の3本だ。残念ながら予想したヒットにならず、国際映画製作者連盟が公認する映画祭(当時は20前後か)で何か賞をもらっている映画にも開放(第2次)が拡大したのである。コンペの正賞ではないがモントリオール世界映画祭で観客賞を受賞した『Love Letter』が滑り込んだ形になり、ふたを開けてみると100万人を超える大ヒットになったのである(今も韓国内の日本映画の実写では1位だが)。映画祭の賞にはこういう効果もあるのだ。
それでも「映画祭」などを立ち上げ、継続して、運営していくことの裏方作業は大変なものである。だからこそ、もっとストレートに「受賞者」関係者が歓喜の渦に包まれ、そのことを誇りに、もっと良い作品を創ることへの糧になるよう願うものである。

かわい しんや
1981年慶應義塾大学法学部卒業後、フジテレビジョンに入社。『南極物語』で製作デスク。『チ・ン・ピ・ラ』などで製作補。1987年、『私をスキーに連れてって』でプロデューサーデビューし、ホイチョイムービー3部作をプロデュースする。1987年12月に邦画と洋画を交互に公開する劇場「シネスイッチ銀座」を設立する。『木村家の人びと』(1988)をスタートに7本の邦画の製作と『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)などの単館ヒット作を送り出す。また、自らの入院体験談を映画化した『病院へ行こう』(1990)『病は気から〜病院へ行こう2』(1992)を製作。岩井俊二監督の長編デビュー映画『Love Letter』(1995)から『スワロウテイル』(1996)などをプロデュースする。『リング』『らせん』(1998)などのメジャー作品から、カンヌ国際映画祭コンペティション監督賞を受賞したエドワード・ヤン監督の『ヤンヤン 夏の想い出』(2000)、短編プロジェクトの『Jam Films』(2002)シリーズをはじめ、数多くの映画を手がける。他に、ベルリン映画祭カリガリ賞・国際批評家連盟賞を受賞した『愛のむきだし』(2009)、ドキュメンタリー映画『SOUL RED 松田優作』(2009)、などがある。2002年より「函館港イルミナシオン映画祭シナリオ大賞」の審査員。2012年「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」長編部門審査委員長、2018年より「AIYFF アジア国際青少年映画祭」(韓国・中国・日本)の審査員、芸術監督などを務めている。また、武蔵野美術大学造形構想学部映像学科で客員教授を務めている。

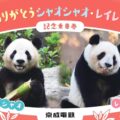




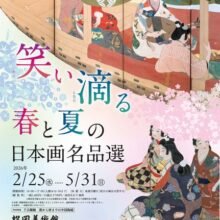
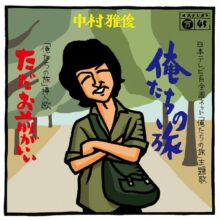

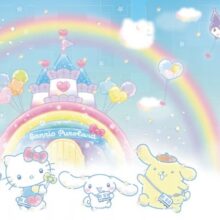

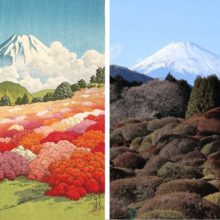

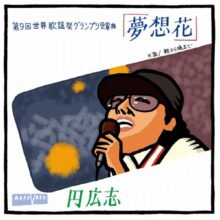



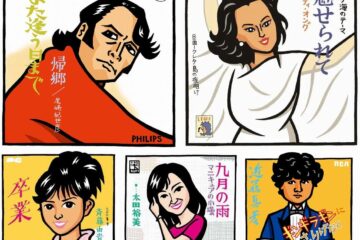




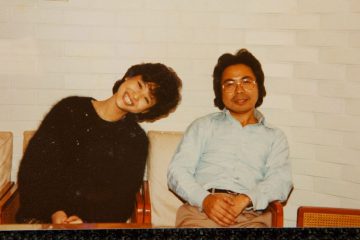
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















