「昭和の姉」とすごした風景
SPECIAL FEATURE 2010年10月1日号より
作家であり脚本家であった向田邦子さんが一人暮しを始めたのは 昭和三十九年十月十日、東京オリンピックの開会式の日、三十五歳だった。東京都港区西麻布三丁目十七番地、昔の町名でいえば霞町。そして昭和四十五年、四十一歳のときに終の棲家となる東京都港区南青山五丁目一番地南青山第一マンションに越した。 忙しい中にも時間を見つけては散歩を楽しんだ向田さんは、つっかけ履きで、住まいの近所を歩き、日常の暮しのなかに四季を発見し、ここは私の縄張とばかりに次々にお気に入りの店を見つけていった。旺盛な野次馬根性、せっかちで、新しもの好きで、頑固で、自慢したがり屋。向田さんの散歩の風景には、向田邦子そのものの気質が見え隠れする。末妹の和子さんとともに向田さんが愛した南青山、西麻布(霞町、笄町)を歩いてみた。向田邦子の散歩道は、和子さんが姉との時間を楽しんだ記憶の風景でもあった。
文=向田和子
撮影:ヤスクニ
向田邦子
作家、脚本家。昭和4年11月28日東京生まれ。昭和 25年実践女子専門学校(現実践女子大学)卒業、財政文化社に入社し社長秘書を務める。昭和27年雄鶏社に入社、「映画ストーリー」編集部に配属。昭和33年に初のテレビ台本「ダイヤル 110番」を共同執筆。昭 和35年には女性のフリーライター事務所「ガリーナクラ ブ」に参加、「 週刊平凡」「 週刊コウロン」などに執筆。昭和37年ラジオ「森繁の重役読本」開始。昭和39年テレビ「七人の孫」開始、人気シナリオライターに。テレ ビドラマの脚本「だいこんの花」「 時間ですよ」「 じゃが いも」「寺内貫太郎一家」「 母上様・赤澤良雄」「冬の 運動会」「眠り人形」「 家族熱」「 阿修羅のごとく」「 源氏物語」「 あ・うん」「 幸福」「 隣りの女」などテレビ史に残る多数の作品がある。昭和53年には初のエッセイ集『父 の詫び状』を刊行。昭和55年には「小説新潮」連載の連作短編小説『思い出トランプ 』の「花の名前」「 かわうそ」「犬小屋」で第83回直木賞受賞。昭和56年8月22日、台湾旅行中に航空機事故で死去。
あなたはどんな散歩日和がお好きで すか。
心が躍った、姉との散歩道
邦子姉との散歩は大雨でも何であれ 一緒に歩くことだけで心が躍るのです。この世を去って三十年もの時を経て、姉の愛した散歩道を私は普段着でそぞろ歩きをすることにしました。
その日は、晴れのち曇りところにより雨。なんてステキ、天候もいろんな顔と表情で挨拶してくれている。出発点は表参道、南青山第一マンション(邦子の終の棲家)からとは粋なはからい。
人も車も程よい活気とリズムを注いでくれ、十分も歩くと根津美術館の樹々と白壁のゆるやかな坂。これは次の舞台への序奏のようだ。
昔の町名でいえば笄町あたり。そこには高層ビルはなく、木造モルタル造りの家々、「あけぼの荘」といった昭和な感じの名前がついたアパート、せ いぜい三階どまりのマンション。小さな公園、小さなベンチ、ゴミのない静けさがある。遠くに視線を向けると、この静寂さはさらに歩みを速めてくる。青山墓地である。なんともいえないおいしい空気があった。樹々となつかしいドクダミ、ネコジャラシ、正式名は判らない草々が自由闊達に主張し ていた。細い道沿いの家では小さな空間をいかしてナス、ゴーヤも育てている。あじさい、あさがお、季節の彩りもわすれない心づかい。
さわやかな生活感、その住人とのたちばなしもまた一服の水で、喉をいやす。そんな風景、匂いが私の記憶を祖父宅へといざなう。六十年も昔へとタイムスリップ。邦子、専門学生の二年程寄宿した麻布市兵衛町の祖父の家。六本木、霞町、青山、渋谷は通学路、いやアルバイトの日々の地図の一ページ。邦子の若い感性にジンワリとしみこんだ生活感覚の基本がここにあった。
このあたりを姉と歩くと早足になり歌をうたったりした。ここは酒屋だった、女優さんの家はあそこ、目も口も手も動き、私はスキップをしてついてゆく。くちなしの香り、一枝欲しいが匂いどろぼうで満足、二人で深呼吸。うれしや、今再びこの細道にくちなしの木、見つけた。心の小ひきだしにメモを入れた。
─私は、身のまわりのものと、共同所有ではない伽俚伽だけを連れて家を出た。東京オリンピック開会式の日だった─ 『眠る盃』より








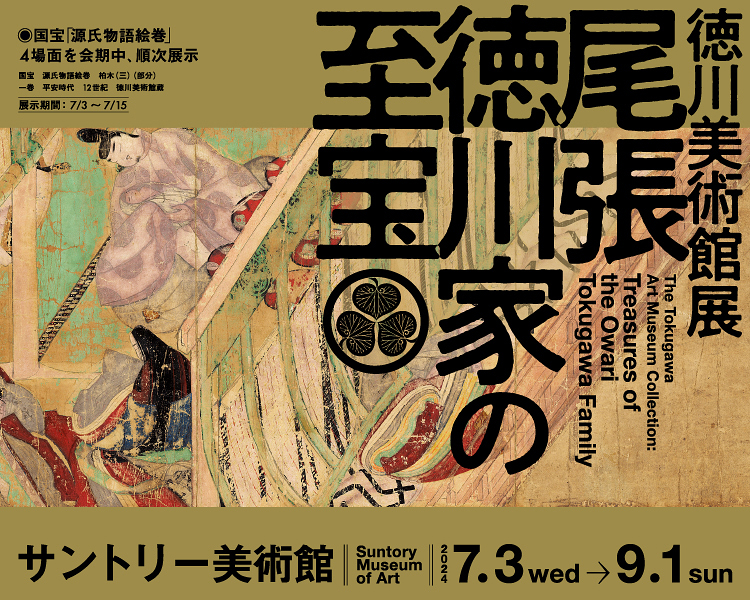

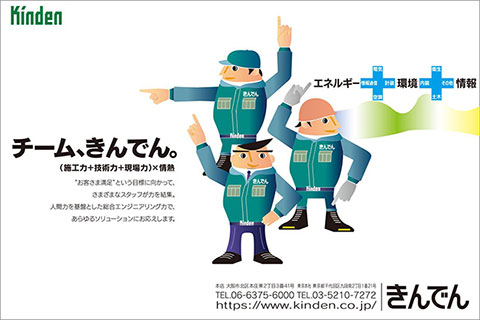

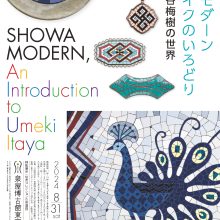

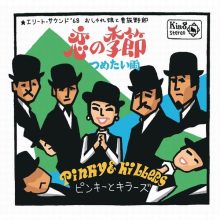

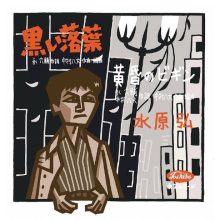




























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)















