黒沢年男の魅力が、あの狂おしいばかりのパッションの発露であったことは言うまでもない。そのワイルドな演技は、三船敏郎を除く東宝俳優(池部良~宝田明~久保明~夏木陽介~加山雄三)の系譜には全く属していない。
目をむき甲高い声で叫ぶ姿は、まさに彼の真骨頂。その代表的作品が、決起ならずに自害する青年将校に扮した『日本のいちばん長い日』(67)であり、川崎の自動車工場で汗まみれで働く若者を演じた『めぐりあい』(68)であることは、どなたも否定されないはず。どちらも若者の鬱屈(現代であれ、戦時であれ)をストレートに爆発させた野獣的演技で、黒沢の代表作に挙げられよう。
しかし、黒沢自身が傾倒していたのは岡本喜八や恩地日出夫ではなく、実は西村潔と出目昌伸という若手監督であった。
西村潔のデビュー作『死ぬにはまだ早い』(69)を見た時の激しくも静かな衝撃は、今でもはっきり記憶している。低予算を逆手に取ったワン・シチェーション劇にして、現実時間とほぼ同時に進行するサスペンス映画は、もうひとつの『恐怖の時間』(64:岩内克己監督・山崎努出演)と言えるもの。本作では、深夜のドライブインに拳銃を持った殺人犯=黒沢が闖入したことで生じる「恐怖の時間」が描かれ、黒沢の破滅的な演技には、観客を圧倒するインパクトが確かにあった。

偶然拳銃を手にした若者の悲劇を描く西村の次作『白昼の襲撃』(70)では、さらに才気走った演出スタイルが見られる。日野皓正のトランペットが炸裂する音楽の使い方も実に巧み(西村のジャズ好き・音楽好きは、ジュークボックスの使い方からもよく分かる)だが、筆者は閉塞感や緊張感の高まりが尋常でない前作のほうに軍配を上げる。ちなみに西村は、『パンチ野郎』のチーフ助監督でもあった。




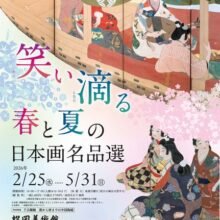
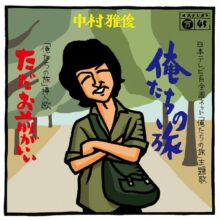

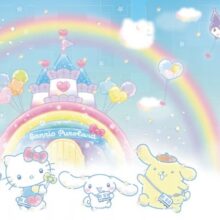

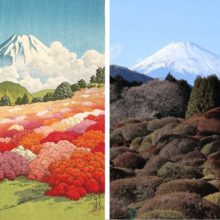

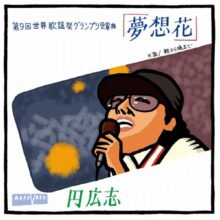



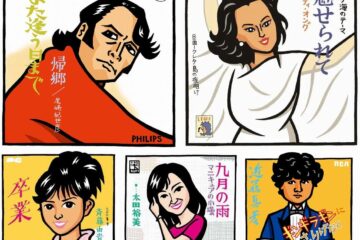




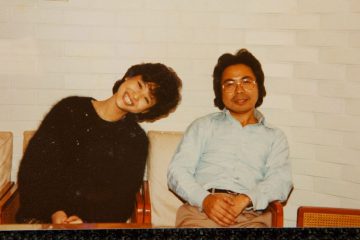
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















