世界的にも評価の高い、彫刻家・舟越桂(1951年5月25日~2024年3月29日)。
父は、戦後日本を代表する彫刻家の舟越保武である。長兄を生後8ケ月で亡くしたことから家族全員がキリスト教の洗礼を受け、中学生ぐらいまで毎週ミサに通う少年だった。やがてラグビーに熱中する高校時代を送る。大学院時代に手がけた函館のトラピスト修道院の聖母子像を契機に木彫の人物像の創作を始めた。大理石をはめ込んだ遠い目をした独特な佇まいの人物像は、一瞬にしてみるものを魅了した。「崇高な何かが現れてくるまで食い下がって制作を続けた父」の背中をみて育った少年は、いつしか父を越えたのかもしれない。今年72歳で逝った舟越の作品群は、55年を経た箱根の森へ。

1951年岩手県盛岡市生まれ。母は詩人の舟越道子。7人兄弟の次男として生まれる。75年東京造形大学彫刻科卒業。77年東京藝術大学大学院研究科彫刻専攻修了。86~87年文化庁芸術家在外研究員としてロンドンに滞在。88年第43回ヴェネチア・ビエンナーレ(イタリア)、92年にはドクメンタⅨ(ドイツ)など世界的な展覧会に出品し、人気・実力ともに世界レベルとなっていった。また天童荒太著『永遠の仔』『悼む人』、辻仁成著『海峡の光』など数多くの文学作品の表紙を飾った。彫刻のみならずドローイングやエッチング、リトグラフ、版画等平面作品で見せる絵画性も評価されている。95年、第26回中原悌二郎賞優秀賞受賞、97年第18回平櫛田中賞受賞、09年、芸術選奨文部科学大臣賞(第59回)、毎日芸術賞受賞、11年紫綬褒章受賞。作品は国内外の美術館に多数収蔵されている。24年3月29日逝去。享年72。
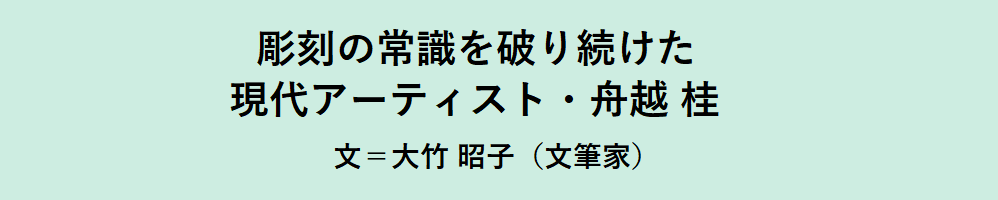
父の背中に感じた威厳の呪縛からの出発
舟越桂の人物彫刻は一度見たら忘れられない。偶然にも作品に再会することがあると、あ、この人知っている、と足を止める。記憶のなかでそれは彫刻ではなく、かつて行きあった人物になってしまっている……。
前に張りだした額、くっきりした顎のライン、長い首、その下に広がるゆったりした肩の稜線、と骨格のフォルムは静かな意志を感じさせる。それとは対照的なのが眼の表情だ。視線の先になにがあるかわからない、不可視の世界を探ろうとしている眼差しのように感じられないだろうか。
人は肉体を抱えて生きながら、肉体を超えたものに憧れる。彼の作品の骨格と眼の対照には、その矛盾が表象されているかのようだ。実体のある世界に生きながらそこに充足できず、見えない世界を手探りする。その行為が放つ色気が舟越の作品に独特のきらめきを与えている。
長崎の二十六聖人像で知られる舟越保武を父にもち、幼い頃から父の仕事場を見てきて、将来自分も彫刻をするだろうという予感とともに育つ。手を動かすのが好きで、ものをつくって生きていくことに疑いはなかった。それは芸術を志すという構えたものではなく、職人の子どもが父の背中を見て直感するものに近かったのではないだろうか。
とはいえ、父はあまりに立派で威厳がありすぎた。恐ろしさに萎縮してしまうほど存在感があり、その呪縛をいかに振りほどくかが桂の出発点となった。
わたしは生前、舟越氏にお会いしたことはない。テレビのドキュメンタリーで拝見したのが最初だったが、そのとき漠然と描いていた神経質でかしこまったイメージが覆されて驚いた。心やさしく茶目っ気たっぷりな人柄がテレビ画面からあふれでてくるようで、作品のポップな雰囲気が少し理解できたような気がした。父の威厳にこのように距離をとりながら自身の世界を築いてきたのだろうと想像させられたのだった。

大学院時代、初めての木彫作品の制作に「楠」を先生から勧められた。楠は堅すぎず、柔らかすぎず、刃がすうっと入っていくのに、ほどよい抵抗感があった。色も匂いも良かった。遠くを見ているような人の表情は昔から気になっていたが、遠いところを見る目は、自己を見つめている目だと、舟越は語っている。より自然に見えるように、目には大理石を使うが、目の表情そのものは、瞼で決まる。





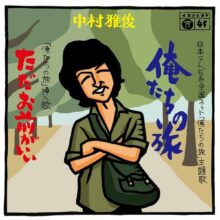







































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















