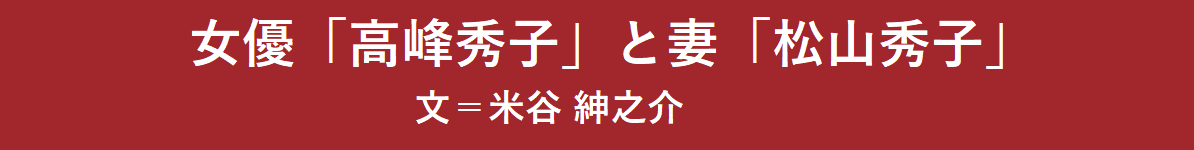
オードリー・へプバーンなら『ローマの休日』、原節子なら『東京物語』と、スターには映画ファンの頭にポンと浮かぶ代表作がある。ところが、高峰秀子にはそんな代表作がない。いや、代表作がないという表現は正確ではない。代表作を選ぶことができないのだ。それほど数多くの名作、秀作に出演している。
5歳で子役として出発し、『綴方教室』で主役に抜擢されたのが14歳のとき。最後の映画出演となった『衝動殺人 息子よ』まで400本近くに出た。出演作の監督を思いつくまま並べれば、木下惠介、小津安二郎、成瀬巳喜男、五所平之助、稲垣浩、豊田四郎、市川崑、増村保造と、圧倒的な顔ぶれだ。黒澤明の名前がないが、17歳で主演した『馬』は監督の山本嘉次郎が掛け持ちで忙しく、実質的にはチーフ助監督の黒澤が撮った作品である。黒澤明は高峰秀子が初めて恋心を抱いた相手でもあった。そんなエピソードを含め、高峰秀子のフィルモグラフィを見ることは日本の映画史を俯瞰することに他ならない。
とりわけフリーとなった1950年代は、『カルメン故郷に帰る』、『稲妻』、『煙突の見える場所』、『雁』、『二十四の瞳』、『浮雲』、『流れる』、『張込み』、『あらくれ』、『喜びも悲しみも幾年月』など、大女優の円熟期らしい仕事ぶりだった。
ぼくがあえて高峰秀子の映画を1本選ぶなら、成瀬巳喜男の『浮雲』だろうか。小津安二郎が「オレには撮れないシャシンだ」と言ったように、世界にも類を見ない、男女の腐れ縁を描いた傑作である。会っては別れ、またよりをもどしてという相互依存の愛憎関係は人間の深淵を見せられるようで、何度観ても成瀬らしい暗く底光りした世界に引き込まれてしまう。高峰秀子のすねたような、あるいは不貞腐れたような表情と声にも磁力があり、諦念や絶望の向こうに女の純情を感じさせられる。

1955年、高峰秀子は『浮雲』が公開された直後に結婚を発表した。相手は松竹の助監督・松山善三。のちに脚本家や監督として活躍するが、このときは明らかに格差婚だった。二人の関係が分かるこんな微笑ましいエピソードがある。初めて銀座のレストランでデートしたときのことだ。松山は「あなたが先に食べてください。僕は真似します」と言い、それを見た高峰秀子は「なんて素直な人だろう」と思ったという。
当時、スター女優の結婚は人気の点でマイナスとされた。しかし、そんな定説を覆すように次々に名作に出演し、仕事に没頭した。考えてみれば、高峰秀子は「子役は大成しない」という定説を覆した人でもある。そして、仕事に没頭したからといって、家庭をないがしろにしたのではなく、家にいるときは家庭に没頭した。高峰秀子にとって家庭は夫婦の共通点を見つけるより、お互いの違いを発見し、認める場でもあった。夫婦とは一心同体などではなく、夫は自分と違うのだから尊重できると考えたのである。










































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)
















