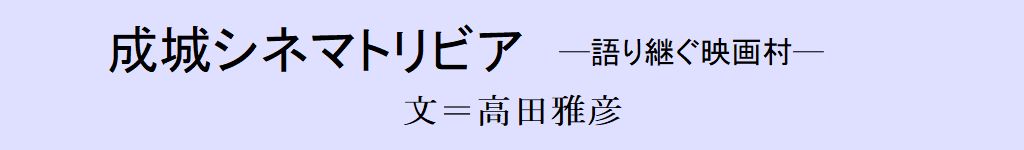
1932年、東宝の前身である P.C.L.(写真化学研究所)が
成城に撮影用の大ステージを建設し、東宝撮影所、砧撮影所などと呼ばれた。
以来、成城の地には映画監督や、スター俳優たちが居を構えるようになり、
昭和の成城の街はさしずめ日本のビバリーヒルズといった様相を呈していた。
街を歩けば、三船敏郎がゴムぞうりで散歩していたり、
自転車に乗った司葉子に遭遇するのも日常のスケッチだった。
成城に住んだキラ星のごとき映画人たちのとっておきのエピソード、
成城のあの場所、この場所で撮影された映画の数々をご紹介しながら
あの輝きにあふれた昭和の銀幕散歩へと出かけるとしましょう。
東宝争議以降、他社で映画を作っていた黒澤明が、久々にホームの東宝に帰ってきて撮ったのが『生きる』(52年)である。〈死ぬこと〉すなわち〈生きること〉の意味を問う‶哲学的作品〟とも言うべきこの映画、4K化されたヴァージョンを改めて眺めると、作劇構成も含めて、ありとあらゆる映画的技法がつぎ込まれた、実にテクニカルな作品であることが分かる。このとき黒澤明32歳、その志気も技量も頂点に達していた時期に撮られた本作は、続く『七人の侍』(54年)とともに、キャリアを通じての最高作と断じてよいだろう(註1)。
今さら内容を紹介するまでもない、この傑作‶病気克服もの〟(こんな一言で表現されるべきではないが)に三船敏郎が出演していないことには、一抹の寂しさは感じるものの、ではどんな役で出たらよかったのかと問われても、何の答えも見出せない。これは、それだけこの映画が志村喬の独壇場であることの証しであり、もし『生きものの記録』(55年)で三船が見せた巧みな老人演技(とメーキャップ技術)が本作で試されたとしても、決してこれだけの感動作にはならなかったであろう。海外にてリメイク話が幾度も起きたことにも、心から納得させられる。

さて、なにゆえに本連載でこの黒澤映画を取り上げるかと言えば、実は本作が成城と祖師谷に深い関わりを持っているからである。砧の東宝撮影所で作られた映画であるから、成城に関係があるのは当たり前。しかしながら、物語の舞台となるのは何処とも知れぬ市役所の市民課。志村喬演じる主人公・渡辺勘治は、そこの課長であるから、黒澤があからさまな成城ロケ場面など見せるはずもない(そう意味では『七人の侍』も、名もなき村が舞台となることから、御殿場で撮影されても富士山の姿は絶対に写らない)。
ところが本作、意外なところで成城の痕跡がフィルムに残っているのだ。














































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















