文=太田 治子
母のそばにはいつも月刊誌『ひまわり』があった。表紙の少女の大きな瞳が私に向いていた。昭和の時代、未婚の母と幼子の私、困窮の果ての居候生活…、それでも今日を美しく生きよう、明日はもっと美しく、と中原淳一の言葉に励まされて母とともに歩んでいた。生誕111年、母と中原淳一は同い年だった。

中原淳一は、前年に創刊した『それいゆ』に続き、昭和22年1月号の創刊号から27年2月号まで67冊の『ひまわり』を刊行した。戦後間もない時期で日本中が豊かではなかったが、全国の少女たちを照らすべく中原は表紙を描いた。
◇母の小説が『ひまわり』に載った
11月末の或る日の夕暮れ、私は横浜駅の地下通路を、東口にある「そごう美術館」に向かって、一人歩いていた。『111年目の中原淳一展』をみたかった。それにしても、111年目とは、どういうことだろう。何やら、意味深いことに思われた。ふと、40年も前に空の上へいった母の言葉を思い出した。
「中原淳一さんと私は、同じ大正2年生まれなのよ」
母は、そう嬉しそうに話した。中原さんが昭和22年から昭和27年にかけて刊行した月刊誌『ひまわり』に、母は恐らく2回にわたり少女小説を発表していた。
「私の小説が、『ひまわり』に載ったのよ」

母がそういったのを、私は確かに記憶している。私がもの心つくか、つかないかのころだったと思う。母と私は、神奈川県葉山の母の弟に当たる叔父の家の離れで居候生活を送っていた。『ひまわり』が廃刊される直前の、昭和27年あたりのことになる筈である。幼い私は、『ひまわり』の表紙の大きな目の少女の顔を、はっきりと覚えていた。その明るい少女の顔と雑誌のタイトルの『ひまわり』はとてもぴったりしていると、幼心に考えた。私はどの絵本のお姫様の顔よりも、『ひまわり』の少女の顔を素敵だと思った。『ひまわり』の雑誌を抱き締めて、母と葉山の海へでかけた。当時の葉山の海はきらきらと輝いていて、表紙の少女の愛らしさにとても似合っているように感じられた。
「この少女は、ママに似ているね」
砂浜に二人で腰かけながら、私はそういった。母も、とても目が大きかった。
「私は、こんなに可愛くないわ」
母そういった後で、
「これからも『ひまわり』に書かせていただけるといいのだけれど」
そのようにポツリといった。大病まもなかった母は、お金がなかった。居候生活を続けながら、少女小説を書いていきたいと思っていた。夢みる夢子さんのまま「未婚の母」として私を生み、〝刀折れ矢尽きる〟の状態で葉山の弟の家にたどりついた母は、まもなく『ひまわり』が廃刊になるなどということは、いささかも気付かずにいたに違いなかった。





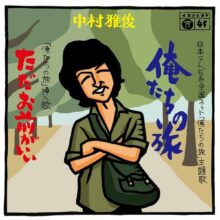







































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















