多くの胸像や頭像と舟越作品はどこが違うのか
ふつう彫刻作品は胸像か全身像のどちらかが多いが、舟越のつくるものはほとんど臍(へそ)から下の部分までが入っている。このことは言われなければ気づきにくい。少なくともわたしはそうだったが、ほかの彫刻とはどこかちがうとは感じており、その理由が胴体が含まれていることにあると知ったとき、思わず、そこだったのか!と声をあげたのだった。
それについて舟越は、胸像や頭像は知性や理性やその人の性格のほうに重点が置かれるが、臍のあたりまであると、ものとしての人間、動物でもある人間の姿が見えてくると説明している。なるほど、腹がすわるという表現があるように腹はエネルギーの源である。そこを含めると、理性や知性で腑分けできない生命そのものの力が強調されるのだ。
素材には楠が使われており、初期の人物像はみな着衣して彩色が施されている。美術大学で裸の全身像をつくらされたとき、なぜ裸でなければならないのかと疑問に思ったという。ふだん人は服を着て過ごしている。自分は特殊な状態にある人間ではなく、自分の横にいるような人物をつくりたいのだ。だとすれば服を着せるのが自然のように思われ、必然的に色も着けることになった。
舟越の彫刻はどれも具象像であり、一見、アヴァンギャルドには見えない。だが、多くの点で当時の木彫像の常識を破っていたのである。

Photo: 齊藤さだむ© Katsura Funakoshi Courtesy of Nishimura Gallery
本作は、東日本大震災がきっかけとなり制作された。盛岡市で生まれた舟越は、被災した故郷に祈るような気持ちを込めて制作したのだろう。
〝見えているもの〟から〝見えていないもの〟へ
人間のことを外から見えているものと、見えていないものの両面から考えたい、と彼は語っている。骨格が外側から認識できるものとすれば、見えていないものを象徴しているのは大理石に彩色したものを埋め込んだ眼球の表情である。眼はもの見るための器官だが、開いていても何事も見ていないことがあるのをわたしたちは日常的に経験している。そのとき、視神経は網膜に映ったものではなく、自己の内側で起きているものに反応している。見るための器官が見えていない世界を感じさせる倒錯。ここにも舟越作品の秘密があるように思う。
初期の作品の多くは街で出会った人などをモデルにして、「見えているもの」を手がかりにつくられた。だが、次第に関心の比重が「見えていないもの」へと移っていく。肩に手が生えていたり、顔が裏と表の両面についていたり、頭に角のようなものがあったりと、異形の人物が目立ってくる。

まず作品とほぼ同じ大きさのデッサンを仕上げる。何十枚も描き、自分で気に入ったものになるまでデッサンに食い下がる。比率では、7対3くらいでモデルのない作品の方が多いようだが、気になるのは、自分の内へと向かう視線を感じさせる人だという。





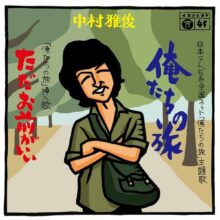







































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















