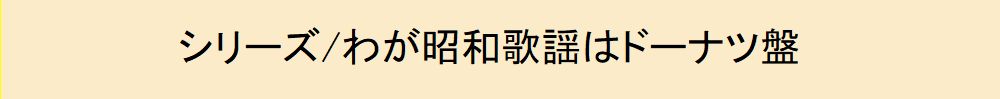
「おい、硝子のジョニーって知ってる? いい歌なんだ」「ショーコのジョニー?」…硝子をガラスと読めずショーコと思い込んでいた。同級生女子の中華そば屋(ラーメン屋とは言わなかった)の壁にズラリと貼り付いていた料理名の短冊(まだメニューなんて気取っちゃいない)の中から「サメコってどんな料理なんだ?」「サメコ? 餃子のことか」…なに?!ギョーザと読むのか! こんな食べ物、知らなかった。仲良しだった吉田君が千葉に転校することが発表されて、先生が黒板に「我孫子」と書いた。「吉田、ワレソンシに行っちゃうのか」…アビコとは読めなかった。1961年(昭和36)、アイ・ジョージの自作曲「硝子のジョニー」(作詞:石浜恒夫)がリリースされた頃、ボクは小学生だった。
我が家は、ラジオからいつも歌謡曲が流れていた。明治生まれの親父はたまに家にいると、浪曲を聴いて泣いていた。しばらくしてテレビが来て茶の間は歌番組が中心になった。姉は流行りの洋楽を口ずさんでいたし、人気の歌手のプライバシーなども話題になるような芸能好き一家だった。ボクは歌謡曲が好きだった。三橋美智也、春日八郎、フランク永井、若手では神戸一郎、井上ひろし、松島アキラ、ジャズ系を歌う旗照夫などなど、大人の歌を意味も分からず大きな声で歌っていた。でも、ほぼ同時期にミッキーカーチス、平尾昌晃、坂本九やジェリー藤尾、飯田久彦、ダニー飯田とパラダイスキングなんかも聴いたり歌い始めたりして洋楽ポピュラーも身近になろうとしていた。
そんな時期に、訳の分からない洋楽だと思いながらもラテン系の音楽がボクの中に飛び込んで来たのだ。「ベサメ・ムーチョ」「ラ・マラゲーニャ」「キサス・キサス・キサス」などの日本でも大ヒットを飛ばしたのは、トリオ・ロス・パンチョス。大きなソンブレロ帽子にレキントギターを抱えて綺麗にハモった歌声と哀愁を帯びた旋律は、原語の歌詞はまったく意味不明でも、ボクの中に心地よく響いてすっかり好きになった。1959年(昭和34)に来日していて、アイ・ジョージが前座をつとめたことは知る由もなかったが、メキシコ人のアルフレード・ヒルを中心にしたトリオ・ロス・パンチョスの楽曲は日本中に流行っていった。白黒のテレビがやっと家庭に入ろうとしていた時代、流行歌にも勢いがあったし、ラテン・ミュージックをカバーする日本人歌手も出始めていた。
アイ・ジョージはそんなラテン音楽ブームに乗って登場してきたのだった。いきなり「ラ・マラゲーニャ」の歌唱で1960年(昭和35)の第11回NHK紅白歌合戦に初出場しているのだ。それまで黒田春雄の名で鳴かず飛ばずの歌謡曲のレコード歌手(テイチク)ではあったが、アイ・ジョージと名乗ってトリオ・ロス・パンチョスの前座歌手となったことが彼の人生を大きく転換させた。いくら前座をつとめたとはいえ、トリオ・ロス・パンチョスのカバー曲で翌年の紅白に初出場できるなど、その歌唱力はすでに定評があったのだろう。因みに、NHK紅白歌合戦には1971年第22回まで連続12回も出場する力量があった。だが…。

本名、石松譲治は1933年(昭和8)香港で生まれた。石油会社の役員だったという日本人の父親と母親はスペイン系フィリッピン人。裕福な家庭に生まれたが一転。幼児の頃母親を亡くし、父親も復員後まもなく譲治が十代半ばの頃亡くなり、戦後は孤児となった。パン屋、菓子屋、運送屋、ボクサーから競輪選手、ハンコ屋など転々と仕事を変えて生き抜いたことは伝説的でさえある。転々としながらも、持ち前の歌のうまさから流しの歌手が着地点になる。ナイトクラブや米軍キャンプが仕事場だったが、まもなくテイチクレコードからプロデビュー。小柄ながら分厚い胸板から発せられる大声量と歌唱力は圧巻だった。1953年(昭和28)デビュー曲のシングル「裏街ながし唄」はボクの耳に届いたことはない。芸名、黒田春雄のキャッチフレーズは〝第二の田端義夫〟だったという。が、前述のようにさしてヒットもせず再び流しの歌手として全国を流転。そのうち大阪の高級ナイトクラブ「アロー」の専属歌手になる。一旦はテイチクレコードから離れていたが、1959年(昭和34)トリオ・ロス・パンチョス来日公演の前座歌手に抜擢され、同じく前座をつとめた坂本スミ子とともにラテン・ブームに乗って売り出すきっかけを掴むことになる。













































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















