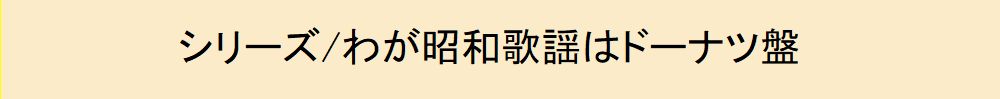
映画『泥の河』(1981年1月30日公開)という名作をご記憶だろうか。
1956年(昭和31)の大阪、安治川の河口で小さな食堂を営む夫婦と9歳の息子、信雄。毎日のように食堂に立ち寄っていた荷車のオッちゃんが事故で死ぬのを目前にする。置き去りにされていた荷車から鉄屑を盗もうとしていた少年、喜一に出会う。忽然と現われた同い年の喜一は、対岸に停泊している屋形船(郭船)で暮らしていた。両親から夜は近づいてはいけないと言われながら交流が始まる。水上生活の喜一と信雄の出会いと別れの物語である。
ボクに刻まれている昭和の記憶は、信雄の父(田村高廣)も母(藤田弓子)も荷車のオッちゃん(芦屋雁之助)も、喜一の母(加賀まりこ)も、懐かしい昭和の大人たちそのものだったし、信雄も喜一の姉の銀子も紛れもなく昭和の子供たちの面影を残していた。「きっちゃーん」と叫びながら、河岸から遠ざかり去っていく喜一の屋形船を信雄がいつまでも追うラストシーンは、荷車のオッちゃんの死から始まり友が去って行き、そしてこれからも続くであろう生きることの悲しみと辛さを幼い信雄に暗示させている。人生とは出会いと別れの繰り返しである。
因みに、この年のキネマ旬報ベスト・テン第1位受賞、日本アカデミー賞優秀作品賞・最優秀監督賞等々多くの映画賞を総なめした名画である。驚くべきは、原作の芥川賞作家・宮本輝(77歳)、メガホンを取った小栗康平(78歳)、9歳の喜一と信雄の設定も、そしてこれから本題に入る日本のポップス黎明期のティーン・シンガー、田代みどり(76歳)、斯くいうボクも含めて、わずか4、5年の間に生まれひしめき合っている、これこそ団塊の世代、同期の桜たちである。

では、なぜ底抜けに明るくハワイのワイキキビーチの太陽の輝きを思わせる、田代みどりの楽曲「パイナップル プリンセス」(1961年=昭和36、東芝音工でリリース)と、まだ敗戦の色濃く残る貧しく暗い昭和の家族の物語『泥の河』が、結びつくのか。奇しくも「もはや戦後ではない」と経済白書が宣言した昭和31年、しかし人々の心には敗戦の傷跡を残し、都会のあちらこちらには瓦礫のままになった空き地があり空襲の痕跡が無残だった。もはや戦後ではない、と言い放った政府を訝しげに疑った時代だった。それでも人々はロカビリーに熱狂し余熱冷めやらぬまま、ティーン・エージャーのシンガーが「テレビの時代」の先頭に立ってブラウン管で笑顔を振りまくようになっていった。













































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















