「北国行きで」が男と女の別れ歌ではあるが、詩を書いた山上路夫は、いわばアメリカ育ち(アーチストとして)の朱里エイコを思えば従来の情念が渦巻くような別れ話にはしたくなかったのではないだろうか。彼女はサバサバとして軽快感のある現代的な女性をイメージしたのだろう。そんなヒロイン像が朱里エイコのキャラクターとマッチすると踏んだに違いない。結果として大ヒットにつながった、といえるだろう。
—いつも別れましょうといったけれど、そうよ、今度だけはほんとのことなの―と女の口から言わせるなんて、よほど強い意志を持っている女だ。歌謡曲の定番のように縋りつくような女々しさがない。—憎みあわない前に、さっさと私は消えて行くの―と潔い。曲もイントロのシンコペーションが軽快で別れ話の重苦しさなど感じさせず、ドラムスの響きがいかにもポップス調だ。1970年代といえば、女性の社会進出、ウーマンリブの運動や男女雇用機会均等法など、時代の背景を想い起こされ、強い女の出現が始まっていく。ジメジメした別れ話など受ける時代ではなくなった。
朱里エイコは、ワーナー・パイオニアでは合計19枚のシングルを発売しているが、35万枚を突破した「北国行きで」だけが突出した売り上げで、あとはほとんど二桁にも届いていない。「日本ではレコードがヒットしないと、テレビにも呼ばれないし、実力が発揮できない」と嘆いた時期がある。(歌が下手でも売れれば勝ちみたいな)日本の芸能界では活動の幅が広がらず、ずっと亜流に甘んじなければならなかった。1972年(昭和47)12月31日 第23回NHK紅白歌合戦(東京宝塚劇場)に「北国行きで」の歌唱で3組目に初出場。白組は堺正章が「運がよければいいことあるさ」を歌唱している。朱里エイコは上下繋ぎの黄金のホットパンツで登場。見事な脚線が目を引いた。翌年の紅白も「ジェット最終便」(ヒット曲ではなかった)を歌唱したが、1番を歌った直後、曲が中断され沖縄・名護の桜の花々を若手アイドルや紅組歌手たちが客席を回って配るという演出が入って、2番の出だしをトチってしまう一幕があった。沖縄返還間もないNHKのお粗末な演出だったが、もしかしたら、あれがケチのつけはじめだったのか。以後、朱里エイコは日本の芸能界から忘れ去られていった。
その後も彼女のスキャンダラスめいた失踪やステージをドタキャンするなど悪い話題は芸能週刊誌ネタとなって繰り返されたが、そのたびに、朱里エイコはアメリカのステージに立って大歓声を浴びている。「日本では歌謡曲を、アメリカではポップスを」というスタンスがどこで狂ったのか、誰も朱里エイコを救えなかったのか。歌唱の実力、声量、明るいキャラクター、もちろんあの脚線美、一ファンとして58歳の死は残念でならない。
文=村澤次郎 イラスト=山﨑杉夫




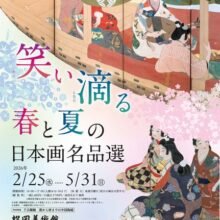
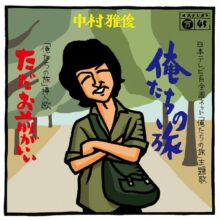

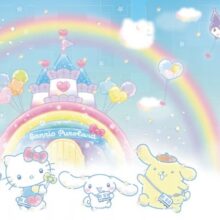

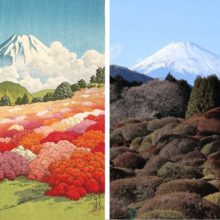

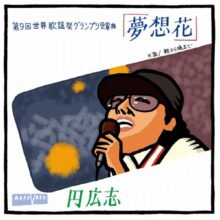



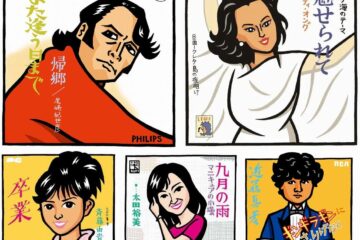




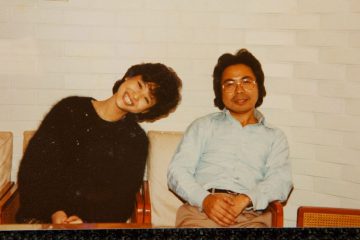
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















