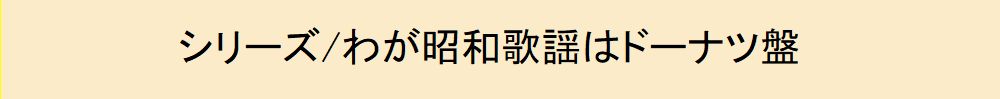
アナログレコードの1分間45回転で、中央の円孔が大きいシングルレコード盤をドーナツ盤と呼んでいた。
昭和の歌謡界では、およそ3か月に1枚の頻度で、人気歌手たちは新曲をリリースしていて、新譜の発売日には、学校帰りなどに必ず近所のレコード店に立ち寄っていた。
お目当ての歌手の名前が記されたインデックスから、一枚ずつレコードをめくっていくのが好きだった。ジャケットを見るのも楽しかった。
1980年代に入り、コンパクトディスク(CD)の開発・普及により、アナログレコードは衰退するが、それでもオリジナル曲への愛着もあり、アナログレコードの愛好者は存在し続けた。
近年、レコード復活の兆しがあり、2021年にはアナログレコード専門店が新規に出店されるなど、レコード人気が再燃している気配がある。
ふと口ずさむ歌は、レコードで聴いていた昔のメロディだ。
ジャケット写真を思い出しながら、「コモレバ・コンピレーション・アルバム」の趣で、懐かしい曲の数々を毎週木曜に1曲ずつご紹介する。
最近のテレビの歌番組には「昭和」の冠を付けたものが多い。ひと頃盛んに「懐かしのメロディー」といった番組があったが、なぜかそうは言わず、「昭和」なのだ。で、昭和といえば団塊の世代がチャンネルを合わせるだろうという、テレビ側の魂胆に嵌まる。お決まりのように、昭和48年(1973)9月に発売された「神田川」(当時は、「南こうせつとかぐや姫」、作詞・喜多條 忠)が、切ないバイオリンのイントロとともに同い年の南こうせつ(73)が登場するのだ。テレビの前には昨年結婚50年の老婆がいて、照れくさいったらこの上ない。毎度チャンネルを変えてしまおうかと迷いながら聞き入っていると、懐かしさと切なさに思わず熱くなるのである。老人特有の涙なのです。
実はドーナツ盤がリリースされた年、すでに結婚して2年目を迎えている。この曲を初めて聞いたのは、いつだったか。3畳一間の下宿ではないが、われわれは6畳一間押入れ付のアパートだった。ベニヤ板の戸を引くと半畳ほどのスペースが入口で、ガス台と水道の蛇口のあるお勝手兼用。手洗い、洗濯場は共用だった。家賃は、1畳当たり千円の時代、諸々合わせて月額8千円。歩いて5分の横丁の風呂屋は、「大黒湯」。入浴代は35円か40円だったか(頻繁に値上げがあった頃)。確かに一緒に出ようと番台越しに風呂屋の時計を見ながら決めていた。亭主の月給2万5千円程度で、もちろん共稼ぎ。同棲ではないが、歌詞と重なるような慎ましく貧しい日常だった。
あるのは若さだけで、怖いものはなかった。ただ、「悲しいかい?」などと問いかけるようなやさしさをひけらかすことなどついぞなく、無口を決め込んでいた。それが今日までつづいている。

後に知ったことだが、作詞の喜多條は、自らの同棲体験を詞に託していた。恋人と同棲していた当時は、学生運動が活発な時代である。ご多分に漏れず喜多條も機動隊と衝突する激しいデモ活動に明け暮れ、疲れ果てて帰ると、彼女は騒々しい社会とは無縁で何事もなく料理などをしながら彼の帰りを待っている。その後ろ姿につい平穏な暮らしを望みたくなるが、それが活動家としての信念を揺るがせ活動そのものが無意味になってしまう。何も怖くなかったが、あなたのやさしさが怖かった、とは喜多條が女性に向けて発した言葉だったという。
そうなのか、と、これにはいささか面食らった記憶がある。どう読んでも、健気な女性目線だな、と思っていた。覚えていますか、あの時代、と女が問いかけている。どんなに貧しくとも二人で暮らす日々が懐かしかったというようにささやかな同棲時代を振り返っている。しかしよくよく考えてみれば、当時の男には喜多條の詞にあるようなやさしい言葉は持ち合わせていなかったのではないだろうか。少なくとも筆者は照れくさくて無口になった。それにしても、「四畳半フォーク」などと揶揄され、暗く切ない「神田川」が、なぜ今でも懐かしい情景とともにこころに響くのか。確かに名曲だが、実は、中年になり老年を迎えた男たちが、とても口に出来なかったやさしいひと言が込められているからではないか。つまり女性たちへの懺悔の歌であり、「こんな生活、悲しいかい?」という言葉は飲み込んで、これまでのわがまま勝手放題を、「すまなかった」のひと言が言いたくて、変わって伝えてくれているのである。これまた老人特有の自虐かも知れない。こんなことを言うと、元気に活動している南こうせつさんに叱られるかな。因みに、筆者が5年ほど暮らしたアパートは、道路の拡幅工事とともに消滅し、大黒湯は立派なビルになっていて、昭和の面影はなに一つ残されていない。
文:村澤 次郎














































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















