
文=平能哲也
コモレバWEBにて「東宝映画スタア✩パレード」を連載中の高田雅彦氏の著書『成城映画散歩』(白桃書房)に、次のような記述がある。
著者の承諾の上引用する。第3章の「成瀬巳喜男と成城」の項だ。
「~そして、黒澤がご近所の青柳信雄監督のお宅で飲み、酔っぱらった時に必ずと言っていいほど語っていた言葉が、『成瀬さんにはかなわない』という賛辞(青柳監督のお孫さん・青柳恵介氏の回想による)。この逸話からも、いかに黒澤が成瀬を尊敬していたかがよく伝わってくる。」
今年2025(令和7)年は、成瀬巳喜男監督(1905-1969)の生誕120年に当たる。
生涯に89本(現存は69本)の作品を残した日本映画の名監督の一人である。
同じ松竹蒲田出身の二歳年上の小津安二郎監督(1903-1963)とは生涯の友人であり、ライバルであった。
同じ映画会社(P.C.L.~東宝)の後輩である黒澤明監督(1910-1998)、溝口健二監督(1898-1956)と合わせて、日本映画の四大監督と称せられることが多い。
四人の監督の中で一般的に最も知名度の低いのが成瀬監督だったが、ここ数年、松竹蒲田から移籍したP.C.L.時代の30年代の作品をはじめ、これまで未ソフト化だった多くの東宝(新東宝、宝塚映画含む)作品が廉価でDVD化され、また一部の作品はサブスクネット配信でも観られる。さらに今後、名画座等での特集上映も予定されている。
鑑賞の機会が増えるにつれて、若い世代など新たな成瀬映画ファンは増えつつある。
成瀬映画は同じ作品を何度観ても面白く、そして新たな発見がある、という成瀬映画ファン・研究歴35年を誇る平能哲也氏が、改めて成瀬映画の魅力とは何かを紐解く。
数多い要素の中から4つの視点に着目し、前編の2つの視点に続き、成瀬映画を楽しむさらなる2つの視点=ポイントを新たにご紹介したい。
第三の視点
落語の名人の語り口のような洗練されたユーモアセンス
成瀬監督や成瀬映画の紹介の際によく登場するフレーズが「ヤルセナキオ」。
成瀬映画の作風<やるせない>から、そんな風に呼ばれていたとされている。実際にそんなフレーズがあったのか、誰が命名したのかまったく不明なのだが、少なくとも私が成瀬会等で直接会話をさせていただいた成瀬組のスタッフ、キャストの方たちの誰からも「ヤルセナキオ」というフレーズは聞いたことがない。これは晩年の玉井正夫(撮影監督)のインタビューでも「私は聞いたことがない」と話している。全員ではないが、「いじわるじいさんと呼ばれていた」という証言はたくさんの方から聞いた。あまり良い言葉ではないが「天邪鬼(あまのじゃく)のような性格」だったらしい。
成瀬映画は慎ましい生活や貧しさの現実の中で、懸命に生きる女や男を描く作品が多い。しかし、1本ずつ丹念に観ていくと、実はユーモラスな場面が多いことに気づくのだ。観客を笑わせようとする「あざとい笑い」ではなく、実に自然で、思わずくすくすと笑ってしまう、いわば名人の落語家の語り口のような、粋で上品な笑い。これは成瀬映画だけでなく、小津映画の中にもある要素だ。二人とも明治後期の東京の出身(成瀬監督は四谷、小津監督は深川生まれ)が共通していて、当然落語の教養は自然に身についていただろう。



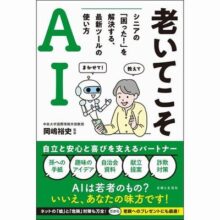




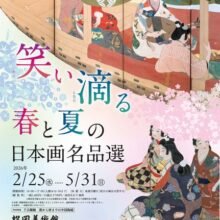
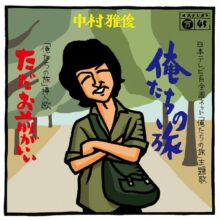

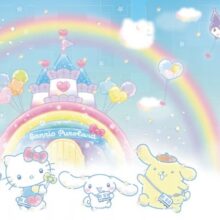




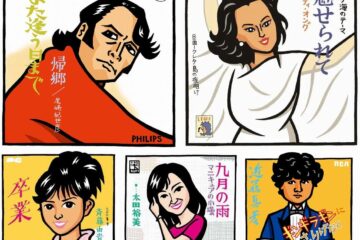




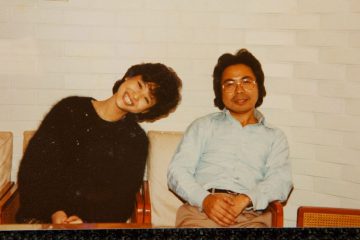
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















