電波ごめんの際どい世相風刺や色言葉に溜飲を下げる
〇月×日 「新宿 末廣亭」。瓦屋根の上がる二階は赤い手すりに白提灯が並び、常連演者の名札、本日出演の額入り白ビラなど寄席文字で埋められ、木戸口でお金を払う昔ながらの寄席定席の雰囲気がいっぱいだ。椅子席の両側はやや高い畳敷き桟敷で、座布団を借りてあぐらをかけば寄席気分満点。上は格天井、舞台欄間は松竹梅透かし彫り、粋な網代の壁を紋入り丸提灯がずらりと囲む。三月上席の昼の部は開始十二時、中入りあって打ち出し四時半まで、演者が十八組も出る。
さあ長丁場だと椅子に深く座り、テンテケテンの出囃子あってまずは落語から。丸坊主の若手は扇子を小皿に見立てて煮豆をフーフー吹いて食う仕草をけんめいに。続く「ハッポウくん」は紙切り芸ならぬ発砲スチロールを切り抜く珍しい芸。できあがった作を「欲しい方」と呼びかけるとたちまち客の手が上がる。当日の演者交替はいつものことで、予定にない漫才「青年団」は教師と学生のピリリと利かせた風刺が小気味よく、相撲呼びだし支度の「一矢」は昨日の出来事を即興漫談、「相撲甚句」に拍子木で〆る。
みんなとてもおもしろい。電波には乗せられない際どい世相風刺や色言葉の「口すべり」は江戸っ子好みに溜飲を下げる。開始に四分の入りだった客はしだいに増え、それにつれて舞台の熱気も上がってゆく。
寄席定席の良さは、知らない芸や芸人に会えること、さらに「あいつは伸びるよ」と通を気取ること。ひいきを追うのもよいが、誰が出ているかに関係なく、ぶらりと寄席に入るのこそ演芸を楽しむ神髄と、しみじみ思ったことだった。

おおた かずひこ グラフィックデザイナー、作家。「老舗になる居酒屋 東京・第三世代の22軒」など




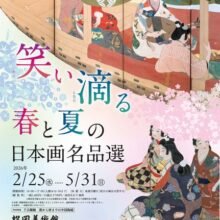
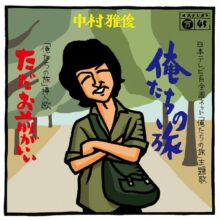

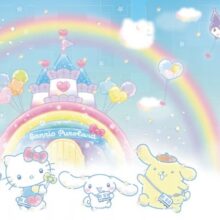

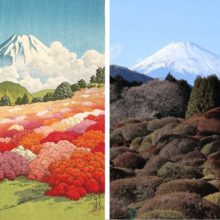

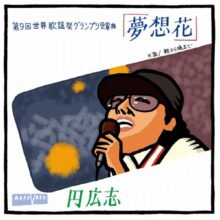



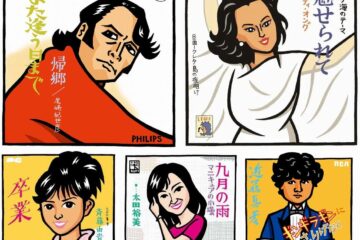




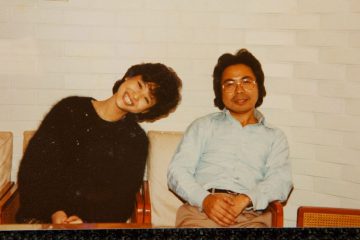
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















