大切にする人の顔を浮かべ皆の安全を祈る
初冬の一日、渋谷の代々木八幡宮を訪ねた。
十数年も続く工事中の山手通りに面した石鳥居脇に、深々とした彫り文字の高い社号標〈代々木八幡宮〉が立つ。裏は〈平成五年九月二十三日 宮司 平岩昌利 稲村雲洞謹書 石工 石銀伊東金五郎〉。代々木八幡宮は作家平岩弓枝さんのご実家で、高校生のとき七五三の受付をされていたそうだ。先代宮司の御尊父は剣の達人で、夜陰に入った賊を眉一つ動かさず木刀で鎮圧したという。
石の急段を上がった高台は一転、梢高く静寂な「渋谷区保存樹林」になり、鳥のさえずる下を猫が悠々と横切る。土の道の敷石伝いに二の鳥居をくぐった由緒板書は、御祭神・応神天皇鎌倉時代初期、源頼家ゆかりの創建とある。脇の石碑は〈鎮座七百八拾年祭 平成御大典記念 獅子頭壱対修理、神楽殿改修、神社神輿修理、石燈籠壱対新設〉の奉賛者名が並ぶ。神社は氏子の浄財で成り立っているのだ。
まずは正殿に身を正し二礼二拍一社。そのときは両親、兄妹、家族など大切にする人の顔を順に思い浮かべる。顔を浮かべることが皆の安全を祈ることになると思っている。しかし今日はもう一つ。先日、妹の娘、つまり私の姪がおめでたと聞き、その安産析願だ。「無事産まれますように」。
正殿の天水受け青銅大甕は〈明治四十二年九月新調 同三十一二年改進〉の古いものだ。堂々たる左右狛犬の「阿」は子を、「吽」は鞠を抱いて威嚇する。一対の大きな石燈籠は明治四十二年、陸軍代々木練兵場建設で移転を余儀なくされた住民が、この地に別れを惜しんで奉納したものだ。〈決別の碑各々其ノ別ルルヲ惜ミ又字ノ消サラン事ヲ想ヒ、茲二燈ヲ納メテ之ヲ紀念トス〉に惜別の情があふれる。
人を幸せにしている代々木八幡宮の「恋みくじ」
木立の中に自然石にブロンズ頭像レリーフをはめた句碑があった。〈そのむかし代々木の月のほととぎす〉作・臼田亜浪 昭和九年建之。〈明治・大正の頃まで、まだこのあたりは東京近郊ののどかな田園地帯であった。〉と解説がある。こういうものを見てゆくのが神社巡りのおもしろさだ。
境内で若い女性が二人、ひいた「恋みくじ」に歓声をあげた。ちょっと見せてもらおう。

一人は〈大吉〝恋の花 二人の愛の咲き揃い 野にも山にも喜びは満つ 〟二人の愛情が苦しかった冬の季節を過ぎて今美しい恋の花と……〉。もう一人は〈大吉 〝神様の導きたまう二人にて今日の出会いを大切にせよ〟幾百万人の男女の中から選ばれた二人なのです。仮初めにも不倫の恋に身を破ることなく……〉。
「へー、よかったじゃない」
「うん、でも全部大吉なのかしら」
「そんなことはない、中吉、末吉もある」
私は力をこめて言った。ここの恋みくじは当ると聞いて二人で遠くから来たそうだ。八幡宮は人を幸せにしている。ちなみに私のひいた普通のおみくじは〈中吉 心を決めていろいろとさわがず迷わず 今までの事をつとめればよし 何事にも手を出してはいけません つねにひかえ目にして事をなさい吉〉だが〈お産安心せよ 難なし〉だった。姪っ子の安産守を買って冬の神社を後にした。

おおたかずひこ
デザイナー/エッセイスト。江戸の総鎮守「神田明神」は近くに行くと必ず寄る。神奈川県伊勢原「大山阿夫利神社」は参道上の巨石に彫り込んだ講や参拝者の名前群が面白い。香川「金刀比羅宮」金毘羅さんは、千三百六十八の石段を上がった展望が壮大だ。




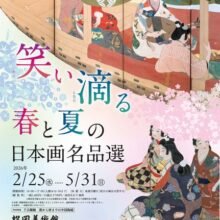
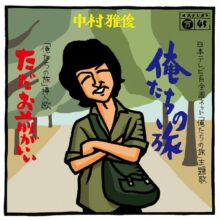

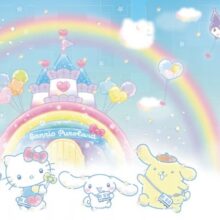

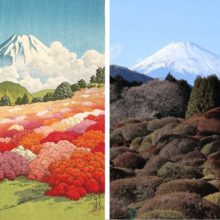

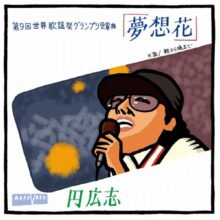



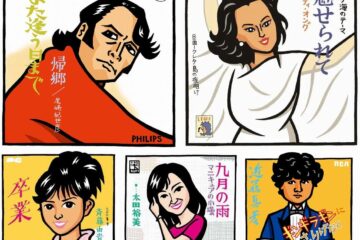




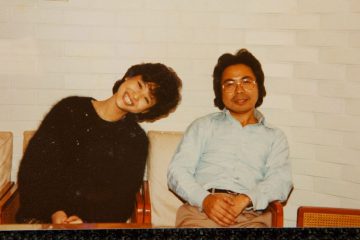
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















