「スフィンクス」というシリーズでは、そこからさらに進んで人間ですらなくなった。山羊のようなべろんとした耳。肩まで届く長いものもあり、首は顔の幅くらいに太く、骨格はしっかりしている。丸く膨らんだ一対の乳房があるが、下半身にはペニスが生えていたりと、人間と動物、雌と雄の境界を超越した摩訶不思議な生き物である。

Photo: 内田芳孝 © Katsura Funakoshi Courtesy of Nishimura Gallery
2000年代に入ると、ドイツ・ロマン派の詩人ノヴァーリスの小説『青い花』の一節から着想した「スフィンクス」のシリーズが登場する。人間を見続ける存在としての「スフィンクス」を題材にした作品を多く残した。
興味深いのは彼らの眼差しである。焦点が定まっていないのは以前と同じだが、そこには悲しみや諦観が滲みでている。いや、そうではない。そのように感じるのは彼らが裸の状態だからかもしれない。眼の部分を前の作品と見比べたあとに視野を拡げて全体を眺めわたすと、視線に感情が滲みでてくる。服の下に隠されていたものがむき出しにされて眼の表情が変化し、感情の在りかを示すのである。
舟越が最初に抱いていたのは自分のすぐ横にいるようなふつうの人間をつくりたいという欲求だった。ところが、彫っていくうちにこういうものができあがった。意図してそうしたのでもなければ、こういう展開を期待していたわけでもなかった。無意識の領域に下降した結果として現れでた存在であり、驚いているのは他ならぬ彼自身かもしれないとも思う。
初期の「ふつうの人間」のほうが好きだという人は多いかもしれない。わかりやすく、親しみやすく、穏やかな印象を与える。だがそこに留まっていたら「ふつうの芸術家」に終わっただろう。後先を省みずに異形の領域に踏み込んだところに、その勇気と想像力こそに、舟越桂が「偉大な芸術家」であるという証があるのだ。

舟越は東京造形大学3年の時にクラスメートを誘いラグビー部を作り、多摩美術大学と対戦した。藝大大学院に入ってからもラグビー熱は続き教授にも呆れられたほど。舟越のラグビー愛が伝わる作品だ。
◎参考文献
『森へ行く日 舟越桂作品集 』
『舟越桂 私の中のスフィンクス』
『彫刻家・舟越桂の創作メモ 個人はみな絶滅危惧種という存在』
『言葉の降る森』『今日の作家たち 舟越桂』

おおたけ あきこ
文筆家。東京都生まれ。ノンフィクション、エッセイ、小説、写真評論など幅広い分野で執筆する。対談やトークの機会も多い。主な著書に『随時見学可』(みすず書房)、『図鑑少年』(小学館)、『眼の狩人』(ちくま文庫)、『この写真がすごい2008』(朝日出版社)、『個人美術館への旅』(文春新書)、『旅ではなぜかよく眠り』(新潮社)、『須賀敦子の旅路』(文春文庫)、『ニューヨーク1980』(赤々舎)、『東京凸凹散歩』(亜紀書房)、『いつもだれかが見ている』(亜紀書房)。最新刊は『迷走写真館へようこそ』(赤々舎)。エッセイと対談のシリーズ「カタリココ文庫」を個人出版している。https://katarikoko.stores.jp




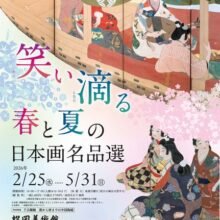
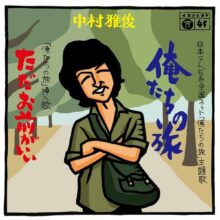

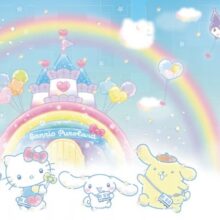

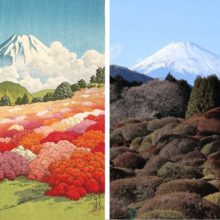

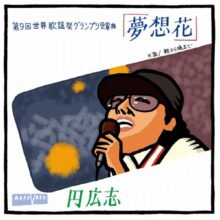



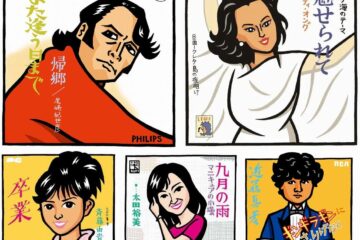




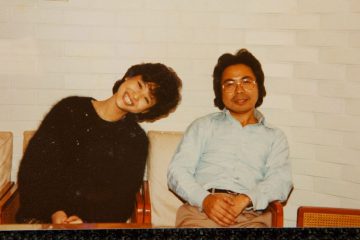
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















