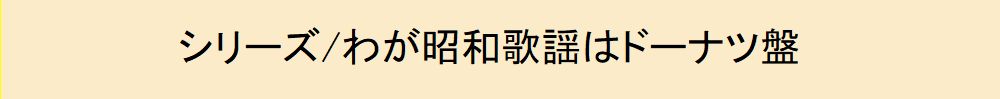
昭和30年代~40年頃、同じ中学校に通う親友・雄二の家は狭い路地の突き当りにあって、一日中陽が当たらず、朽ちてしまいそうな平屋だった。雄二とは仲が良く一緒に遊んでいたが、14歳になる兄の孝は発達障碍があっていつも青っ洟を垂らしていた。もう一人長男の幸一は18歳前後だったか、めったに家に近づかない男だった。たまに派手な上っ張りを着て帰ってきていても、余り近づくことがなかったのは、いかにも不良っぽい匂いを漂わせていたからだった。雄二の父親とも、やはり滅多に顔を合わせなかった。南方の戦地から復員後、肺結核を患っていて、辛うじて治癒したものの床に臥せってばかりだった。ときどき苦しそうな大きな咳が外まで聞こえていた。5人家族の彼と同様、ボクの家も5人家族で互いに貧乏を競い合うような暮らしだった。同じような家族が数軒ひしめき合って暮らしていた昭和の東京・城北の、下町の風景はどこも似たり寄ったりだったのではないだろうか。
テレビは「水道完備ガス見込」という日本教育テレビ(テレビ朝日)の昼帯のホームドラマがあった時代で、水道が通っている家がうらやましいし、都市ガスではなくプロパンガスのコンロが普及しはじめていたが、薪と釜でごはんを炊いている家庭が多かった。子どもでも、「初めちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣いても蓋とるな」というごはんの炊き方の秘訣を諳んじていた。夕餉の支度は、どこの家からも七輪の煙が立っていた。
職人だったボクの父親は宵越しの金は持たない主義だったし、母は手内職をしながら糊口をしのぐ暮らしだった。ただ貧乏が負いでもなく卑屈にもならず互いに見栄もはらない開けっぴろげな〝向こう三軒両隣〟で、近所同士、仲が良かった。「今日もコロッケ明日もコロッケなのよ、あのさ~ちょっとソース貸してくれない?」と、路地の三軒先のおばさんは返す気がないウースターソースを借りに来るし、「芋の煮っころがし、余っちゃったから食べて」と持って来てくれるおばさんもいた。各戸の炊事洗濯は共同の井戸を代わるがわる使っていて、それぞれの家族の事情は井戸端の会話で精通してしまうほどだった。井戸端会議とはよく言ったものである。
ただ雄二の母親だけは、いつも手拭いを首に巻いて朝早く出掛けていった。化粧っ気のない日焼けした顔のしわが深かったが、ときどき見せる笑顔が人懐っこくてボクは好きだった。忘れられない光景がある。夏の日の夕方、おばさんは仕事帰りに買ってきた泥のついた太い大根数本を井戸で洗いながら、ぶつぶつと呟くように、歌っていた。
~~~とうちゃんのためならエンヤコラ、ゆーちゃん(雄二)のためならエンヤコラ、たかちゃん(孝)のためならエンヤコラ、もひとつおまけにエンヤコラ、こうちゃん(幸一)のためならエンヤコラ~~~
大根を洗い終わるまで、同じエンヤコラを歌い続けて、井戸の汲み上げ漕ぎを交互に手伝っていたボクと雄二に屈託のない笑顔を向けた。「ジロちゃん、大根煮て後で持っていくからね」と言った。雄二のおばさんが甘辛く煮込んだ大根は大好物だった。その時雄二の顔を覗き込みながら、とうちゃん、ゆーちゃん、たかちゃんに続いて、「こうちゃんのためなら…」と歌っていたのが、何となく嬉しかった。長男のこうちゃんは、再婚したときの夫の連れ子で、雄二のおばさんから遠ざかるのが、ボクには何となく理解できていたが、それでも、こうちゃんのためなら、と歌ったおばちゃんの優しさが沁みた。

終日ニコヨン仕事(日雇い労働)をして、帰ってからも炊事洗濯で働き続けても、おばさんは笑顔を絶やさない人だった。さかのぼる昭和31年(1956)頃、『ニコヨン物語』という日活映画があってかすかに記憶しているが、山谷の日雇い労働者たちの悲喜こもごもを笑いとペーソス溢れたドラマとして描いていた。三國連太郎、西村晃、大坂志郎、丹下キヨ子、山岡久乃ら、のちにテレビドラマを席巻する懐かしい俳優たちのドヤ街を舞台にしたニコヨン生活物語だった。昭和30年代、泥だらけになって〝土方仕事〟で働きつつも、人情があって明るく生きるニコヨンたちの物語と、雄二のおばさんが重なっていた。













































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















