日本で生まれたのは、おそらく江戸時代に浮世絵など木版画の文化がすでにあったからその応用として考えられたのではあるまいか。
ろう引きの原紙に鉄筆で字を刻む。いわゆる「ガリを切る」仕事の専門の人間を筆耕といった。
宮沢賢治は、若き日、東京に出て来た時に本郷にあった謄写プリントの会社で筆耕の仕事をしていた。『ガリ版ものがたり』によれば、この会社では大正時代にすでに東大の講義内容をガリ版で刷って学生に売っていたという。知恵者がいたわけだ。
昭和に入ると、筆耕は学生の手頃なアルバイトになった(ちなみに「アルバイト」という言葉が使われるようになったのは戦後。それまでは「内職」。)
昭和の暗い青春を描いた田宮虎彦の短篇「絵本」(昭和二十五年)には、昭和戦前期の貧しい大学生が、生活費を稼ぐために「ガリを切る」仕事をしている様子が描かれている。
大きな病院で仕事を貰って来て下宿でガリを切る。一枚いくらの賃仕事で、量をこなすしかない。
田宮虎彦の「絵本」をはじめ「菊坂」「足摺岬」の三つの短篇を合わせた映画、新藤兼人脚本、吉村公三郎監督の『足摺岬』(54年)では、昭和九年ごろの東京で暮す大学生、木村功が筆耕の内職をする。
町の小さな謄写版印刷所から仕事をもらってくる。大学におさめる文書らしい。
下宿で夜、ガリを切る。やすり板の上にろう引き原紙を置き、鉄筆で字を書いてゆく。静かな室内に、鉄筆がやすりに触れるガリ、ガリという音がしてゆく。まさにガリ版。
簡単に出来そうだが、もちろん技術がいる。学生の内職ではなかなかうまくゆかない。出来上がった原紙を印刷所に持ってゆくと、主人に「このあいだのはなんだ、百枚も刷らないうちに破けてしまったぞ」と怒られてしまう。熟練になると、原紙がなかなか破けないのだろう。
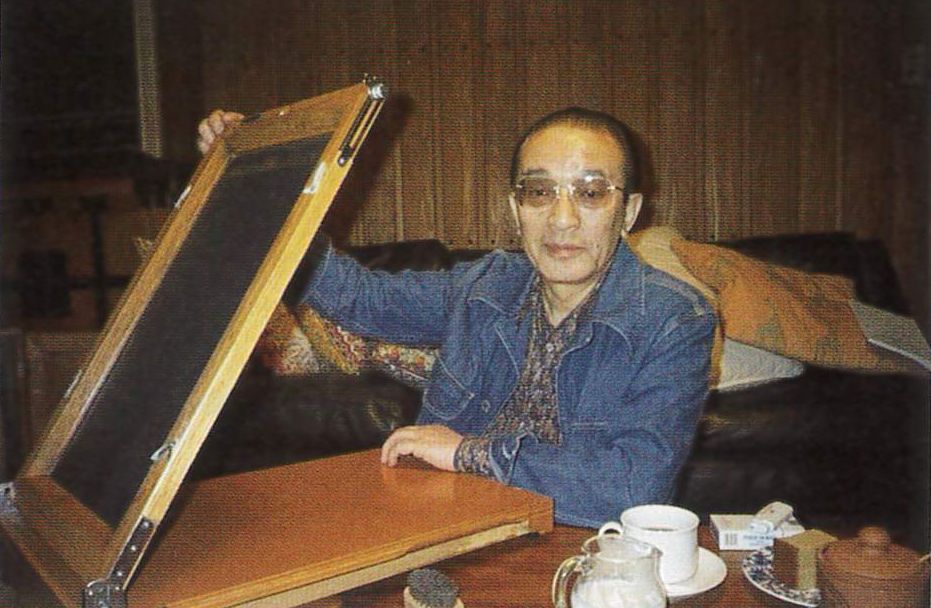

先生と生徒の絆を結んだガリ版刷り
ガリ版は学校教育の現場で広く使われるようになった。とくに戦後、民主主義の時代になると、学級新聞作りが盛んになり、ガリ版は子供にとっても親しいものになった。
昭和十四年生まれの作家、林えり子は回想記『暮しの昭和誌』(海竜社、09年)のなかで、小学校の時、先生がガリ版刷りをするのを手伝った思い出を懐かしく書いている。
「学校に手間暇かかる道具があって、それが先生と生徒の絆となったことを、忘れないようにしなくてはならない」
先生と生徒が一緒になってガリ版で文集を作る。山形県の山のなかにある中学校の先生、無着成恭(むちゃくせいきょう)とその生徒たちの学級生活を描いた今井正監督の『山びこ学校』(52年)では、ガリ版が活躍する。
無着先生(木村功)は子供たちの作文集を作ることを思いたつ。文集作りには子供たちが積極的に参加する。先生がガリを切る。男子生徒がローラーで刷る。女子生徒が刷り上がったワラ半紙を折って製本してゆく。
まさにガリ版が「先生と生徒の絆」となった。良き時代である。
このガリ版を悪用したふとどき者もいる。獅子文六原作、千葉泰樹監督の『大番』(57年)では、ギューちゃん(加東大介)が若き日、ガリ版という便利なものがあることを知り、役場のガリ版を拝借して、なんとラブレターを大量に印刷する。もちろん宛名のところは空欄。めぼしい女性に次々に付け文してゆく。
ガリ版のこういう愉快な使い方もあったか!
昭和のはじめ、まだのどかな時代だった。
かわもと さぶろう
評論家(映画・文学・都市)。1944年生まれ。東京大学法学部卒業。「週刊朝日」「朝日ジャーナル」を経てフリーの文筆家となりさまざまなジャンルでの新聞、雑誌で連載を持つ。『大正幻影』(サントリー学芸賞)、『荷風と東京『断腸亭日乗』私註』(読売文学賞)、『林芙美子の昭和』(毎日出版文化賞、桑原武夫学芸賞)、『映画の昭和雑貨店』(全5 冊)『映画を見ればわかること』『向田邦子と昭和の東京』『きのふの東京、けふの東京』『いまも、君を想う』『それぞれの東京 昭和の町に生きた作家たち』『銀幕の銀座 懐かしの風景とスターたち』『小説を、映画を、鉄道が走る』(交通図書賞)『君のいない食卓』『白秋望景』(伊藤整文学賞)『時には画の話を』『いまむかし東京町歩き』『美女ありき―懐かしの外国映画女優讃』『そして、人生はつづく』『映画は呼んでいる』『ギャバンの帽子、アヌールのコート:懐かしのヨーロッパ映画』など多数の著書がある。













































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















