時代は激変していた。
1968年は学生運動が最も激しかった年だ。古い世代と新しい世代が世界中でせめぎあっていた。当時はカウンターカルチャーと呼ばれていた。と言っても大人たちから見れば「今時の若い者は」というしょうもない不良たちの遊びにしか見えなかっただろう。
ヴィレッジ・シンガースにはそうした時代性が薄かった。オックスはそこを超えたフィクションのファンタジーのようだった。
中世の王子様のようないで立ちでの5人組。それでいて歌っていたボーカルや演奏中のオルガンが失神してしまう。ロックコンサートだったら過激なロックバンドとして目をつけられそうな彼らが歌っていたのが「ガール・フレンド」や「ダンシング・セブンティーン」「スワンの涙」だった。
オルガンを効果的に使った少女趣味な言葉と上品なメロデイーのロマンティシズム。泥臭さとは無縁な夢見心地のカタルシスは飽和状態でマンネリになっていたGSシーンに咲いた最後の花のようだった。
GSは歌謡曲の形を変えた。
ギターだけではなくドラムとベースが前面に出る。「ひとりGS」という言葉も生まれた。68年12月に出て筒美京平の最初のナンバーワンヒットとなったいしだあゆみの「ブルー・ライト・ヨコハマ」は代表的な曲だ。足取りが軽くなるような跳ねた8ビートと一体になった言葉の吹っ切れた心地よさはオックスにもなかった。

時代の変化を決定づけたのが71年に尾崎紀世彦が歌った「また逢う日まで」だったことは言うまでもない。
何が決定的だったか。
あのイントロである。
それまでの歌謡曲の中で認知度が一番低かったのが「編曲」だろう。高らかに突き抜けてゆくホーンセクションが全てを変えた。「編曲」の重要さを証明したという意味でも歴史を変えた一曲だった。








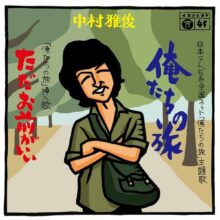







































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















