◇栃若時代とともに
戦後の大相撲を大きく沸かせたのは「栃若時代」と言われ、栃錦(第44代)と若乃花(第45代・初代若乃花)です。二人は軽量小兵にも関わらず、横綱を射止めました。「技の栃錦」、「土俵の鬼、若乃花」と並び称されるほど、二人は大型の力士に対し獅子奮迅の活躍をした横綱です。私がNHKに入局したちょうど昭和28年、テレビ中継が始まり相撲人気がますます高くなっていく時期と重なります。
栃錦は、昭和29年秋場所に横綱に昇進しました。祝賀会があって大勢の祝い客が帰った後、元横綱栃木山の春日野親方に言われたこと。「今日からは、辞めるときのことを考えて過ごせ、桜の花の散るごとく」と、たったそれだけを伝えられたのです。
「初めて聞いたときはなんて冷たい師匠だと、思ったけれど、それが本当に奥の深い重みのあることだったんだよ、杉山君」
と何度も何度も聞かされました。
昭和35年3月場所、14勝全勝同士の若乃花と千秋楽に対戦し、若乃花が全勝優勝しました。この対戦の裏話に面白いことがあります。全勝優勝が懸かっている千秋楽の前夜、若乃花は興奮して眠れず、夜の10時過ぎに深夜映画館に行ったのですが、目が慣れるまで立って見渡すと、そこにちょん髷をした人が一人座っている。目を凝らしてみたら、なんと栃錦だったのです。「栃錦関も同じ気持ちなんだな」と気持ちが落ち着いて回れ右をして帰ったといいます。翌日大熱戦の末、若乃花が全勝優勝。栃錦は次の場所で引退するのです。まさに、師匠の言葉を実践するがごとく、桜の花が散るごとく引退したのです。
第45代横綱・若乃花は、昭和21年11月場所初土俵。青森県出身の10人兄弟の長男で激しい気性と厳しい荒稽古と相まって〝土俵の鬼〟と呼ばれました。昭和30年9月場所11日目、当時関脇だった若乃花は、天下人の横綱千代の山と対戦しました。大熱戦になって水入り、まだ勝負がつかない。それで二番後取り直し、また決着せず再び三度取り直し、水入り。熱闘17分を超えました。結局勝負は「引き分け預かり」。69年相撲に携わってきましたが、後にも先にもこんな相撲はありません。この大一番は相撲史に残ります。

さて若乃花は10勝4敗1分の成績で終え大関昇進を諦めていましたが、千代の山の師匠出羽の海親方(横綱常の花)が審議会議で「(横綱千代の山との大一番を評価して)若乃花を大関に」という発言で、大関昇進が決定しました。上に立つ人、出羽の海さんはトップリーダーとしての見識を見せました。普通なら大関になるには勝ち星が足らない、やめておけとなりますから。先輩のNHKの河原アナウンサーがラジオカーの無線で大関昇進の一報を受信し本人に知らせに走ったのです。当の若乃花は箱根の温泉に休養に行く途中、阿佐ヶ谷の青梅街道で信号待ちをしていたところで昇進が伝えられました。気をよくして発奮し、横綱を目指した大関・若乃花は、苦手の右四つ力士に立ち向かえるよう猛稽古をします。横綱鏡里、千代の山、大内山など右四つの力士に勝つため右四つの稽古を続け、通称・仏壇返しという技を身に付けるのです。
昭和の時代、最も小兵だった横綱若乃花は栃錦の後を追って辞めたかった。しかし後継者を育てるまでやめるにやめられない。横綱になったら後継者を育てることも大事な仕事です。大鵬、柏戸、北葉山、大麒麟、琴櫻、清國らに胸を貸して猛稽古をつけました。昭和35年秋に一人横綱になった若乃花は、一年半後、大鵬、柏戸の横綱昇進を見届けて37年春、引退して二子山部屋として独立しました。
10年周期で、時代は変わると言いますが、昭和36年に大鵬、柏戸が横綱になり、いわゆる「柏鵬時代」が始まります。


すぎやま くにひろ 昭和5年、福岡県生まれ。昭和28年3月早稲田大学第一文学部を卒業し、NHKに入局。大学在学中には「早稲田大学アナウンス研究会」を創設した。名古屋、福岡、大阪、東京各放送局に勤務。入局以来大相撲、野球、オリンピックなど各スポーツ放送の実況アナウンサーとして活躍。大相撲は入局から一貫して担当した。昭和62年10月18日定年。NHK専門委員、BS放送にも携わる。現在、東京相撲記者クラブ会友、日本福祉大学生涯学習センター名誉センター長、同大学客員教授として週2回名古屋で講義を持つ。著書に『土俵一途に 心に残る名力士たち』(中日新聞社)、『土俵の真実』小林照幸氏と共著(文藝春秋)、『土俵の鬼 三代』、『兄弟横綱 若貴の心・技・体』(講談社)他。




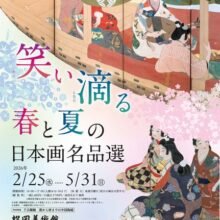
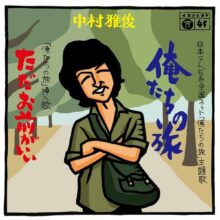

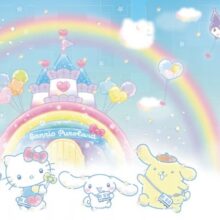

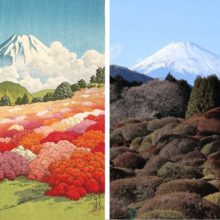

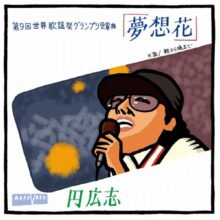



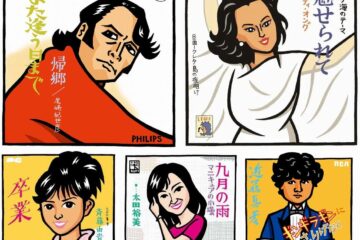




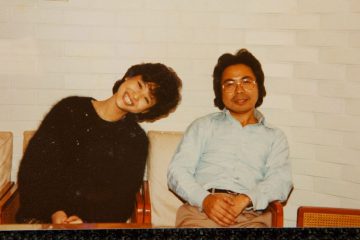
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















