主人公の不安定な心の状態を浮き上がらせる毎熊のモノローグ
『安楽死特区』は映画を観る側の気持ちもぐらぐらと揺るがせる、観る者を巻き込む映画である。毎熊演じる章太郎が面接で主治医ら3人の医師に向き合い話をするシーンがある。章太郎は難病を26歳で発症し9年を経過し余命半年と宣告されている。いわゆる指定難病と呼ばれる病気を患っているのだが、章太郎は、そもそも〝難病〟という言葉自体間違っていると呼吸するのもおぼつかない状態で訴える。〝生かされている〟という表現も侮辱している言葉だと。アシストしてくれている人にはすごく感謝しているが、全部その人によって生かされているのではない。一人ひとりがちゃんと〝生きている〟んだと主張する。そして、安楽死という選択はまだない、苦しい思いをしても生きることしか考えていないと、安楽死を否定する。
まるでラップのパフォーマンスのように、次々と言葉が出てくる。言葉に対する繊細な感性が、死と向き合っている章太郎の心の揺らぎや、心の表と裏を映し出しているようで興味深い。

「章太郎自身も気づいてないんですが、自身の心の内の感情と、人と対面でしゃべっているときに、その相手がたとえ身近な家族であろうと、そのときに口をついて出る言葉が、必ずしも一致していないのではないかなと。出てくる言葉に嘘はないんですよね。でも反面、本当は心でこう思っている自分がいるんだけれども、それを認めたくない思いから、自分にも言い聞かせるような裏腹な言葉が出てくる。自分は確かにもう弱っている、身体もそうだし、心もどちらかというと、安楽死には否定的な考えで特区に入居したものの、安楽死という考えに傾いているかもしれない、でも傾いちゃいけないという、すごく不安定な状態に章太郎の心はあるんだろうなと思えるんです。ラッパーだから、言葉に関してはいろんなひきだしを持っている。そんな人物だから、しんどいながらもつらつらと、言葉がわいてくる。ラッパーとしてステージにも立っているので、言葉で論破してやるという気持ちと、発する言葉と真反対の気持ちが同居していて、だから、それが繊細に映るのかもしれないですね」
主治医はそんな章太郎の心を見透かしたように、安楽死という選択を実は検討しているのではないかと訊ねる。
「このシーンで〝やってあげている〟〝やってもらっている〟という事実は変わりませんが言葉の表現一つについても考えさせられます。その人がどの立場で、どの視点で人に向かっているのか、こちら側、あちら側で表現が変わってしまうようなことにまでさりげなく言及するようなそういった要素が入っているところにも、この映画は素敵だなと感じます」
病を抱えている人にとっては、言葉一つをとりあげてみても、とても重く、デリケートに響いてくるのだと感じさせられ、観る者は、自分につきつけられているように感じられるだろう。














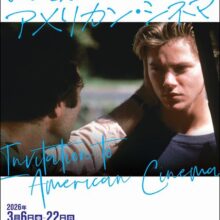



































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















