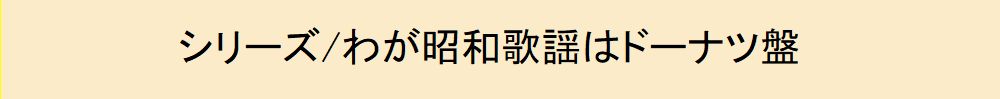
梅雨明けが発表され、いよいよ夏本番だ、「そうだ恋の季節だ!」と慌てて本稿を書き始めた同じ日の56年前、つまり1968年7月20日にピンキーとキラーズ(Pinky & Killers)の「恋の季節」(作詞:岩谷時子、作曲:いずみたく)がリリースされた。何という偶然か! 夜明けのコーヒーを二人で飲もうよ、とボクは連発して女子に近寄っていた十代の不良少年最後の夏(季節)だった。
山高帽を被りステッキを手に黒いタキシード姿のピンキーとキラーズ。ドラムス(パンチョ加賀美)、ベースギター(ルイス高野)、ギター(ジョージ浜野)、ギター(エンディ山口)という4人の男たちのコーラスの中心に16歳のリードヴォーカル今陽子(ピンキー)がいた。強烈な印象のデビューだった。ちょっと気障(キザ)で粋な大人の男たちに囲まれた彼女の、大柄で、ふっくらとした身体から発せられる声量に圧倒された。ラテン音楽を思わせ、ボサノヴァのような雰囲気の楽曲は、メロディーも詞も今までの歌謡曲にはなかった。パンチョ、ルイス、ジョージ、エンディと洒落たニックネームの男たちもカッコいいオジサンたちだった。
忘れられない恋に燃えたあの季節、青いシャツを着て遠い目で海を見つめていたあの人と、私は海辺で裸足になって小さな貝の舟を浮かべて涙ぐんでいたっけ、あの人は死ぬまでひとりにしないと言ってくれたのに……今は冷めてしまったが、女性の燃えるような恋心を歌っていながら、演歌のようなメソメソした未練がましさがなく、どこか都会的な洗練されたセンスを感じさせ、品があった。だいたい夜明けのコーヒーをふたりで飲もう、なんて気障なセリフを発せられるのは青山か六本木か遊び慣れた男に違いないと思いながら、どこかに憧れすら感じてしまったものである。
実は「夜明けのコーヒーふたりで」と作詞した岩谷時子は、このセリフを、越路吹雪から聞いていたのだった。海外公演の折、越路がフランス人の俳優に口説かれていることも知らず、帰国の準備があるからと断った、というエピソードである。それが「男と女が一夜を共にする」の暗喩であったことを越路は後になって知ったという。そのエピソードを聞いて、さすがフランス男だ、と妙に納得した覚えがあるが、越路のマネージャーをしていた岩谷の瑞々しい感性が、このセリフを蘇らせたことにも納得したことであった。

ボサノヴァのリズムにはじめて触れたのは、アルバイト先のスナックのオーナーが暇を見つけては「SERGIO MENDES BRASIL’66 MAIS QUE NADA(セルジオ・メンデス・ブラジル‘66 マシュ・ケ・ナダ)」のLP盤を大事そうに店内に持ち込んで聴いていたからだった。モダンジャズを聴いていた高校生が、ラテン音楽に触れ、セルジオ・メンデスでボサノヴァを知った。この名盤のジャケットがそのままCDになっていて、数年前に手に入れたが、今でも時々聴いてはひとり悦に入っている。1960年代半ばから世界的に大ヒットしたボサロック曲「マシュ・ケ・ナダ」の〝ノリ〟が好きだった。他にもビートルズの「デイ・トリッパー」や「フール・オン・ザ・ヒル」をボサノヴァ風にアレンジし、「ナイト・アンド・デイ」など聴きなれたポピュラー曲のカヴァーが収録されているから、オーナーが口ずさむのと合わせるように歌っていた。スナックの常連客の中にもこのアルバムをリクエストする人が結構いた。一人ひとりの思い出をここで書くつもりはないが、著名なグラフィックデザイナーや小説家の女性など個性的な大人がひとり佇む店だった。「恋の季節」の和製ボサノヴァ・グループが登場するわずか1年前のことである。














































-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















