展覧会までの道のりとこれから
─── それにしても、世界がコロナ禍の影響がある中、大規模なインスタレーション作品を含めて多彩な130点を集めて設置するには相当ご苦労があったと思います。
片 岡 展覧会の入口を飾る、フィリダ・バーロウの大型のインスタレーションは、コロナ禍で作家の来日が叶わず、リモートで設営することになりました。まずロンドンの彼女のスタジオで模型を作り、設営現場にはiPad5台を設置して上からも横からも確認できるようにし、オンラインで作家とやりとりしながら、作品を組み立てていきました。

フィリダ・バーロウは、1960年代から美術学校で教鞭をとりながら、5人の子供を育て上げた。2009年に定年退職後、ロンドンで開催した二人展「ナイリー・バグラミアンとフィリダ・パーロウ」をきっかけに国内外で注目される。物資が乏しいロンドンで幼少期を過ごし、身の回りのものを手作りしたり、第二次世界大戦の空襲によって内部が剥き出しになった建物やがれきの山からも強い印象を受けたことが、今にも崩れ落ちそうな構造や立ち上がりそうな形状といった自身の作風に影響を与えたという。見るものに、直感的で、感情的な体験をもたらす表現が一貫している。1944年英国、ニューカッスル・アポン・タイン生まれ、ロンドン在住。
萩 原 コロナ禍で一人も来日することができなかったんですね。それは大変だったでしょう。
片 岡 ZOOMをセットしてくれるようなアシスタントがいるアーティストはオンラインでのやりとりが可能ですけれど、メールだけのやりとりで進めなければいけない人もいました。本当はオープニングに全員がそろって、記念写真を撮りたかったのですけれど。
─── 萩原さん、アナザーエナジー展で印象に残った作品は?
萩 原 僕は最近、アーティストになっているので、自分だったらこうするよという形でしか見ません。最近、ある美術館が僕の全作品を所蔵してくれたんです。もう嬉しくて(笑)。だから1世紀待った106歳のカルメン・ヘレラの気持ちと同じです。版画をやっているときに、中原佑介さんがリバプール・ビエンナーレに推してくれたのですが、そのころは広告の仕事もしていて芸術の仕事などできない状態でした。だから反省して、作品を見る時は、人の作品としてみないで、自分の作品のネタとしてみています。
その中でも、韓国のキム・スンギが、「クリエイティブは自分を消すこと」と言っていましたが、よくわかるんです。表現というのは、自己主張でなく、自分を消し去ること。寺山修司も物凄い量の仕事をしながら、自分を消し去る作業をしていました。作品はすごく面白くて、自分がなくなってしまうというのが理想です。

1946年東京生まれ。2016年から「萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち 前橋文学館」の館長を務めるかたわら、数年前から、離れていたアートの創作活動に戻る。今年、これまでの自身の全作品が美術館に収蔵されることになった。祖父朔太郎の没後80年にあたる2022年、全国35の文学館などが参加する展覧会「仮称・朔太郎大全」が実施される。
片 岡 彼女は韓国の伝統的な文人教育を受けていて、東洋思想の基礎もありながら、70年代のフランスに行きました、今回、《森林詩》という詩の朗読パフォーマンスと彼女自身のビデオ作品をランダムに組み合わせた映像インスタレーションを展示しています。フィックスされた映像ではなく、東京の天候によりアルゴリズムが映像を決めていくので、毎日変わっていきます。また、世界中の100人以上の詩人や芸術家、哲学者によるポエトリー・リーディングを会期中の満月の日の夜に実施し、ライブ配信しています。
萩 原 録画じゃなくて生ですか。翻訳もしない。面白いですね。
片 岡 一般の人が他者の詩を読んだり、詩人が自分の詩を読んだり、三面スクリーンにいろいろな人が登場します。

キム・スンギは、祖父が道教の研究家、母親が書道家で、幼少期から伝統文化に親しんでいた。1971年にフランス政府奨学生としてフランスへ移住。本展では、コロナ禍を受け、より大きな森羅万象を作品にしたいと《森林詩》を制作した。作品は自身の63本のビデオ作品がランダムに繰り返される映像と、オンラインで開催される詩の朗読パフォーマンスを組み合わせた3チャンネルのビデオ・インスタレーション。1946年韓国、扶餘(プヨ)生まれ、パリ在住。


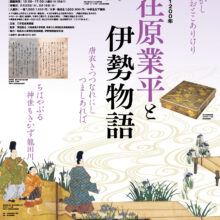


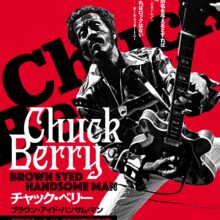
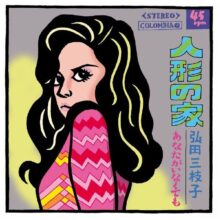




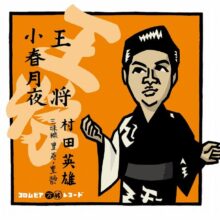



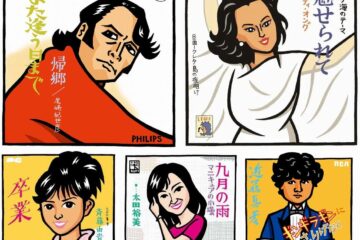




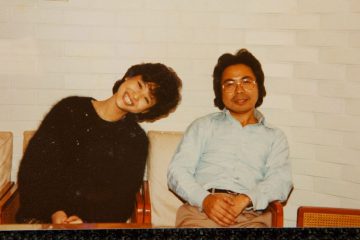
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















