東宝ミュージカルの誕生

新帝国劇場は、昭和四十一年九月に開場した。その開場記念として十月は歌舞伎公演があり、八代目幸四郎(白鸚)の二男萬之助が華々しく二代目吉右衛門を襲名した。以来、帝劇では何度か歌舞伎が上演されたが、私の眼からは〈なんとなく歌舞伎は新しい帝劇にフィットしていないな〉と映った。それよりも、兄の染五郎(現幸四郎)の『王様と私』や『ラ・マンチャの男』が、この劇場には似つかわしいというおもいが強かった。
その年の十一月から翌年にかけて上演された菊田一夫脚色・演出の『風と共に去りぬ』が帝劇のミュージカルに火をつけたのは確かだろうが、なんといっても昭和四十二年九月初演の東宝ミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』のエネルギーは強烈だ。森繁久彌主演のこの作品は、日本で初めて大劇場でのロングランを定着させたのだ。ユダヤ人の集団が理不尽に村から追い出されるという、一見、地味にみえるミュージカルだが、何度やっても客が詰めかける。私は不思議でならなかった。
初演の時の尾崎宏次の評(「演劇界」昭和四十二年十月号)にこうある。
「この作品がたのしく見られた一番大きな理由は、音楽の色彩感とでもいうようなものと、なんというか、場面のシャープな処理とでもいうものであった。それは、結局、脚本ともつながることなのだが、できごと、心情などを〈できるだけ単純にしたこと〉が、私には一番関心をひくことがらであった」(できるだけ単純にしたことに、傍点)(傍点筆者)

この尾崎氏の〝単純〞ということは演劇にとって大切だ。
作品はすべからく豪華絢爛だけがいいのではない。幹がしっかりしていて、単純だが枝葉(えだは)が繁っているように見えるのがいい。そしてなによりも、楽しくわかりやすいのがいい。これが演劇の根本だと私は思う。『屋根の上のヴァイオリン弾き』というミュージカルはその要素を備え、しかも、上演するたびに洗いあげていったのだ。
森繁久彌は、この作品を演劇人生の集大成と心得て名演をみせ、また共演者が家族の如く和して芝居を盛り立て、観客を感動させた。舞台と客席が一体となって、まるで渦巻のように帝劇を呑みこむようなムードが、このミュージカルにはいつも存在した。『屋根の上のヴァイオリン弾き』は、やがて次の世代のロングラン『レ・ミゼラブル』や『エリザベート』にのり移っていく。




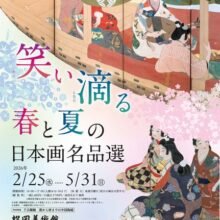
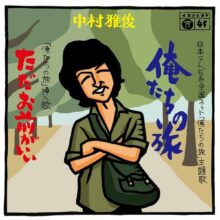

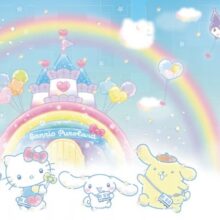

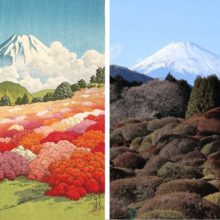

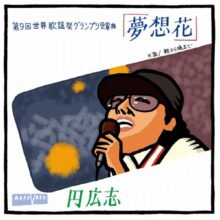



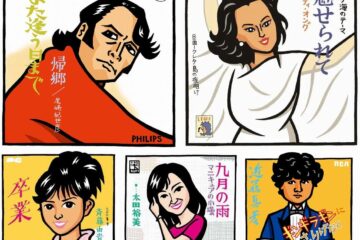




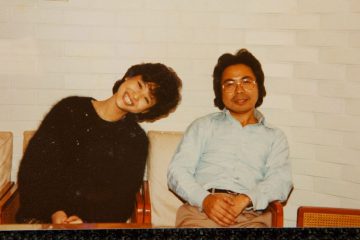
























-817x1024-1C-360x240.jpg)
-scaled-360x240.jpg)


















